SLAVIC STUDIES
/
スラヴ研究
フレーブニコフの言語創造の理念と未来派の前衛精神
北見 諭
Copyright (c) 1998 by the Slavic Research Center( English / Japanese
) All rights reserved.
1. はじめに ― ロシア・モダニズムの二つの傾向
マテイ・カリネスクは美的モダニティに関する研究書の序論で以下のように述べている。
ここでわれわれが扱わねばならないのは、美の不変で、超越的な理想という信念に根ざす伝統的な永遠性の美学から、その中心的
な価値が変化と目新しさであるような、瞬間性と内在性を特色とする美学に至る、文化の大きな転換現象である。
(1)
美を決して変わることのない永遠の価値とするのではなく、不断の変化、「新しさ」を追求して常に前進し続ける運動、カリネスクによれば、それがモ
ダニズムであり、さらには「急進化され、ユートピア化されたモダンの一つ」
(2)
、アヴァンギャルドの運動である。
こうしたモダニズムの特徴付けは広く承認されているように思われるし、ロシアの「急進化されたモダン」、未来派の美学にもそれは妥当する。彼らのマニ
フェストや理論には、「新しい」という言葉が自己規定として、あるいは当為として、特権的な価値を付与され、繰り返し用いられる。たとえば以下のような言
葉は、そうしたモダンの意識を典型的に表すものといえるだろう。
実際、任意の詩作品、及びその作品がわれわれに与える印象に目を向けるなら、〈……〉新しいもの、オリジナルなもののみがわ
れわれの思考や印象の塊に切り込んでくることに気づくだろう。〈……〉その作品が新しいものでありさえすれば、どんな厚かましさ、どんな過ちに対しても、
詩人を許してやらねばならない。結局のところ、芸術において起こりうる唯一の過ちは模倣であり、それは時間の法則という普遍的な法則を破壊してしまうもの
なのだ。
(3)
「新しさ」は詩の至上の価値なのだ。詩人は何よりも新しさを追求して前進しなくてはならない。未来派はカリネスクの言うモダンの典型、その急進化
した形態なのである。
この論文で中心的に取り上げるフレーブニコフも、未来派の運動に参加した詩人である。したがって、彼のラジカルな創作方法、大量の造語を用いて作
品を構成するという方法が、新しさを追求する未来派特有の技法の一つと見なされてきたのも当然のことかもしれない。しかし、実際にはそうではない。後に見
るように、フレーブニコフの言語創造の狙いは、現代の分裂したスラヴ諸語を解体し、それらの祖語として「全スラヴ語」という超越的な原初の言語を再構築し
ようとすることにあった。つまり、フレーブニコフは不断の変化を求めて造語を行ったのではなく、むしろ変化の背後に不変の本質を見いだそうとして造語を
行ったのだ。彼の試みは、たしかに未来派に受容され、そこで前衛的実験として読み換えられることになるが、彼自身の理念は「変化と目新しさ」を求める未来
派の前衛精神とはまったく異質であった。だが、この異質性については十分には指摘されてこなかった
(4)
。フレーブニコフ自身が言語創造の基付けをほとんど行っていないこともあって、彼の試みは
どうしても未来派の言説を背景にして理解されることになり、前衛的な実験として表象されてしまうからだ。フレーブニコフの言語創造の理念を未来派の前衛精
神とは切り離し、彼自身のテクストに基づいて明らかにする必要があるだろう。
だが、そうすると問題がもう一つ生じる。フレーブニコフが「新しさ」を追求するのでなく、逆に不変の本質を志向していたのだとすれば、彼の試みは
モダニズムとは無縁の特異な例外なのだろうか。そうではない。ロシアでは近年、全体主義との関連でアヴァンギャルドを(むしろ否定的に)再考しようとする
動向があるが、そこでは上述のカリネスクとは異なる様相でモダニズムが捉えられている。たとえば、ボリス・グロイスは次のように言う。
通説には反するが、ロシアのアヴァンギャルドはテクノロジーに熱狂していたわけではないし、進歩に対するナイーブな忠誠など
まったく抱いてはいなかった。
(5)
グロイスは特にマレーヴィチを例として挙げながら、ロシアのアヴァンギャルドが「進歩の前衛」であろうとするものではなく、むしろ「際限のない進
歩を止め」ようとするものだったと指摘する
(6)
。
グロイスによれば、ロシアのアヴァンギャルドの真の目的は、進歩によって破壊された世界に調和を取り戻すことにあった。かつての芸術家は神の創造
物である調和的な世界を模倣しようとしたわけだが、アヴァンギャルドはそうした調和がテクノロジーによって破壊され、消失してしまったところから出発し
た。彼らが過去の芸術を否定するのも、外的世界の模倣という方法が、もはや世界に調和が存在しない以上、彼らにはまったく意味が無いからである。そうした
方法と絶縁した彼らは、マレーヴィチの「黒の方形」にその典型的な例が見られるように、絶対不変の超越性(「それ以上還元不能な、超空間的、超時間的、超
歴史的なもの」)を構築し、それに基づいてカオティックな世界を再編=全体化することを試みた。不変の超越性によって進歩を止めるとともに、それを操作し
て世界に調和を取り戻そうとしていたということだ。「テクノロジーの進歩がもたらした無秩序の後には、全世界の再編という単一の全体的なプロジェクトが現
われるのであり、その中ではかつての神の場所は分析的芸術家が占めることになる」
(7)
。
グロイスにしたがえば、ロシアのアヴァンギャルドは進歩を称賛して表層的な「新しさ」を求めるような運動ではなく、むしろ進歩に対抗し、それを停
止させるような不変の「絶対」を求める運動だったということになる。ヴャチェスラフ・クリツィンも、これと同様なことをロシアのモダニズム全体に関して指
摘している。今世紀前半の「文化プロジェクト」は「外面的には極めて多様であるが、その基礎においては『神の死』という同一の出来事を有しており、何らか
の方法でこの空白になった(しかし消滅してはいない)場所を埋めなくてはならないという必要性を感じている」
(8)
。シンボリズム、
アヴァンギャルド、社会主義リアリズムといったモダニズムの企てはすべて、失われた超越性を何らかの方法で取り戻そうとする試みだったということだ。
こうしたモダニズムの特徴付けは、最初に引用したカリネスクの規定にある「変化と目新しさ」を追求するというモダニズムのイメージとはまったく対
立するものであり、グロイス自身が言うように、「通説には反する」ものである。しかし、フレーブニコフの言語創造の試みは、まさにこのようなものであっ
た。彼の造語は未来派の前衛的な実験と同様の外観を持つものではあるが、実際には言語の失われた超越的な起源を再構築しようとする試みだったのであり、そ
れは「変化と目新しさ」ではなく、不変の「絶対」を追求しようとするものであった。グロイスらの一見逆説的に見える見解は、それによってフレーブニコフの
言語創造の理念をム「新しさ」を至上の価値とする未来派の言説の中で不可視化されていた理念を、その本来の文脈にしたがって把握するための枠組みとなりう
るものだ。
だが、注意しなくてはならないが、「変化と目新しさ」を求める未来派の前衛精神をフレーブニコフに適用できないのと同様に、グロイスらの指摘する
アヴァンギャルド像も決して一般化することはできない。それを一般化すれば、今度は逆に未来派の前衛精神を不可視化してしまうことになるだろう。後に見る
ように、未来派の詩人は決して超越性を回復しようとはしていなかった。むしろ彼らはそれを徹底して排除しようとさえしていた。フレーブニコフと未来派の詩
人は、同一の運動に参加してはいたものの、実際にはまったく異なる志向を有していたのである。重要なのは、根本的に異なるこの二つの傾向のいずれをも見落
とさないことである。
失われた超越性を回復しようとするフレーブニコフの言語創造の理念は、実はシンボリズムの中心人物、ヴャチェスラフ・イワノフの影響下に形成され
た理念である。結果的にそれはシンボリストには受け入れられず、逆にそれに対抗する未来派に受容されることになるのだが、それは本来はイワノフの提唱する
シンボリズムの課題を言語の分野で遂行しようとする試みだったのだ。この論文では、このようなフレーブニコフの言語創造の理念の成立の過程と、さらには未
来派によるその受容の過程を考察する。その狙いは、第一に不可視化されていたフレーブニコフ自身の言語創造の理念をシンボリズムとの関連において明らかに
することであり、第二に、超越性の回復というシンボリズムの志向と、「変化と目新しさ」を追求する未来派の前衛精神という、まったく異質な二つの傾向を、
フレーブニコフの言語創造の理念との関係を手掛かりにしながら比較検討することである。
2. イワノフのシンボリズムとフレーブニコフの言語創造
ここではイワノフのシンボリズム論との影響関係を検討しながら、フレーブニコフの言語創造の理念の成立過程を明らかにする。
イワノフはシンボリズムの代表的な詩人であり、フレーブニコフはそれに対抗する未来派に参加した詩人である。しかし、両者の間に一時期親密な交流
が存在し、フレーブニコフがイワノフの影響を強く受けていたことは広く知られた事実である
(9)
。さらには言語の問題に関しても、フレーブニコフの理念の中心にある「全スラヴ語」という
概念が、実はイワノフから継承したものであったということは、フレーブニコフのイワノフ宛の手紙からすでに明らかな事実となっている
(10)
。これらの事
実から両者の影響関係はすでに明らかであるとも言えるが、ここではそうした事実によってではなく、あくまでも理論的に、すなわちイワノフとフレーブニコフ
のテクストの解読を通して、フレーブニコフがイワノフからシンボリズムの文脈そのものを継承し、その中で言語創造の理念を成立させていること、そして何よ
りもその理念が、失われた超越性の回復というシンボリズムの課題を言語の分野で遂行しようとするものであったこと、こうした点を明らかにすることにしたい
(11)
。
2-(1) イワノフのシンボリズムと全体性の回復
そこで、まずはイワノフのシンボリズム論を概観しておこう。ロシアの後期シンボリズムが「観念的で宗教的」
(12)
な運動だったことはよく指摘されることだが、それを端的に示すのが彼らの二元論である。彼らは可視的・経験的な現実(現象界)の背後に、それを超越する高
次の現実(本質界)が隠されているものと見なし、それを把握することを試みる。そして、イワノフによれば、それを可能にするものこそが「シンボル」であ
る。イワノフにとってのシンボルは単なる修辞上の技法ではない
(13)
。それは詩人を高次の現実、本質界に触れさせる神秘的な媒体なのである。
シンボリズムとはシンボルに基づいた芸術である。〈……〉それは、周囲の現実の現象のうちに別の現実の兆候であるシンボルを
開示することで、現実を意味深長なものとして提示する。別の言葉で言えば、シンボルは地上的、経験的な意識の領域だけではなく、それとは別の領域に存在す
るものの関連や意味を意識できるようにするのである。
(14)
シンボルはもう一つの現実の「兆候」である。シンボルは経験的な現実の中にありながら、同時にもう一つの現実である本質界の超越性を分有している
のだ。詩人はこうしたシンボルを媒介にすることで、経験的な現実を越え、その背後に隠された超越的な本質界を把握できるようになる。そして本質界を把握し
た詩人は、その結実として、そのもう一つの現実をイメージによって開示するような「神話」を産み出す。「シンボルは神話の潜在形態、その萌芽形態」
(15)
なのである。イワノフのシンボリズム論において重要なのは、シンボルから産み出される、この「神話」である。
イワノフにとって神話が重要なのは、それが単なる詩人の創作物であるにとどまらず、失われた全体性を社会に取り戻させるような「全民衆的な大芸
術」
(16)
であるからだ。
イワノフによれば、かつての「有機的時代」にはプリミティヴな文化が存在しており、そこでは人々の間に単一の基本観念や共通了解が存在していた。
しかし、この「有機的時代の文化」はすでに崩壊しており、現代はそれにかわって登場した「批判文化」が支配する時代である。この文化の中では「グループや
個人、信仰や創造行為が孤立化し、それらが公共的全体性からの分離を自ら認めている」
(17)
。個人主義が栄え、社会が細分化しているのだ。そして「最近、勝利を収めた実証主義」
は、この「批判文化」が人類の到達する最終段階であると見なしているが、イワノフにとってはそうではない
(18)
。シンボリス
トの創造する神話、シンボルから生成する神話が、このように分裂した社会を再び結合させるような可能性を秘めているからだ。イワノフにとって、シンボリズ
ムは「新たなる有機的時代」を「予感」する芸術なのである
(19)
。
神話は自由な空想の産物ではない。真の神話は集団的な自己確立の公理であり、〈……〉ある種の本質あるいはエネルギーの一つ
の位格なのである。個人主義的で、普遍妥当性のない神話というものはありえない。形容矛盾である。なぜなら、シンボルはその性質上、個人主義を越えたもの
であり、それゆえ言葉と同じように、しかし普通の言葉よりも力強く、個人の神秘的精神の最も内密な沈黙を、全世界の共有思想、共有感覚のための器官に変え
てしまうような力を有しているからである。
(20)
イワノフは、神話が普遍妥当なものであり、集団的な自己確立の公理になるものだという。イワノフがこのように言うのは、神話が超越性を分有するシ
ンボルから産み出されるものであり、超越的な本質界の「一つの位格」として成立するからだ。神話はその超越性によって、すべての者に妥当するような普遍性
を有するのであり、個人主義や社会の細分化を産み出すような現象界のあらゆる差異を乗り越える。神話はあらゆる者に了解可能な共同性の原理となりうるので
あり、それによって分裂した社会に再び全体性を回復させうるのである。
イワノフのシンボリズム論の概略は以上のようなものである。それはまさに失われた超越性を回復することで世界の調和を取り戻そうとする試みに他な
らない。シンボルの媒介によって超越的な本質界を把握し、その結実である神話によって公共的全体性を回復すること、それがイワノフのシンボリズムの課題で
ある。
ところで、こうしたイワノフのシンボリズム論の一つに「詩人と俗衆」という論文がある
(21)
。この論文でもシンボルから神話を産み出し、それによって全体性を回復するという基本的
構図に変更はないのだが、この論文ではとりわけ「民族」が問題になっている。フレーブニコフは特にこの論文に影響を受けていると思われるので、この論文に
関しても簡単に触れておくことにしよう。
この論文でイワノフが課題にするのは、一体性を喪失した民族に全体性を取り戻すため、失われた「民族精神」を回復させることである。現在、ロシア
民族は社会階層の分化によって一体性を喪失しているが、古来の民族精神を回復することでこうした分裂を克服しようというのである。そしてそれを可能にする
のも、やはりシンボルである。通常のシンボルが現象界と本質界を照応関係によって媒介するのに対し、ここでのシンボルは詩人を失われた民族精神に触れさせ
るような媒体である。「シンボルは、すでに失われ、忘れられてしまった民族精神の遺産である」。ここでのシンボルは、失われた民族精神の痕跡のようなもの
であり、本質界の超越性を分有するのではなく、失われた民族精神を記憶にとどめるものなのだ。詩人が行うのは、このシンボルに残された記憶を回想し、それ
によって失われた民族精神を回復させることである。イワノフは言う。
認識とは回想であるというプラトンの教えは、詩人が民族の自己意識の器官であるのと同時に、またそのことによって民族の回想
の器官でもある以上、詩人にも妥当する。詩人を通して民族は自己の古来の魂を想起し、数世紀の間そこに眠っていた可能性を回復させる。
プラトンがイデアを想起するように、詩人はシンボルに残された民族の記憶を回想し、その詩人を通して民族全体も自己の失われた精神を回想する。そ
うすることで失われた民族精神を回復させ、民族の一体性を取り戻そうというのである。そして、それはやはり神話の創造という方法で行われる。
真のシンボリズムは全民衆的な大芸術の中で詩人と俗衆を和解させねばならない。隔絶の時は過ぎ去ろうとしている。われわれは
シンボルの小道を通って神話に至る。大芸術とは神話創造的な芸術である。シンボルから成育するのは、古来から可能性の中に存在していた神話であり、それは
精神の民族的・全世界的な自己確立の内在的な真理をイメージによって開示するものである。
ここでもシンボルから産み出されるのは、集団的な自己確立を可能にする「神話」である。神話によって民族は分裂を克服し、かつての一体性を回復さ
せるのだ。
このように、この論文でも基本的な構図に変更はない。ここでのシンボルは現象と本質ではないものの、民族精神を有する超越的な起源とそれを喪失し
た現代という、それと等価な二つの領域を媒介しているのであり、ここにも二元論的な構図や媒介者としてのシンボルの機能などは存在している。またシンボリ
ズムの課題も、詩人が超越的な領域に触れることで神話を創造し、それによって分裂した社会に全体性を取り戻すという点では同じである。ただ、より具体的な
ところで言えば、ここでのシンボルには民族の記憶という属性が加えられ、詩人の課題も記憶の想起という行為に変わっている。フレーブニコフへの影響を見る
うえでは、こうした点にも留意しておく必要がある。
2-(2) フレーブニコフの言語創造の理念
フレーブニコフはこうしたイワノフの論考を通してシンボリズムの文脈を継承し、自身の言語創造の理念を成立させているのだが、そのことは彼の最初
期の論文「スヴャトゴールの塚」
(22)
から明らかにすることができる。この論文はきわめて断片的でメタフォリカルであり、それを解読するのは容易ではないが、この論文の基調をなすのもやはり民
族の問題である。たとえばそこには次のような断片が含まれている。「『私に口を下さい! 私に口を下さい!』という大地の声にわれわれは耳をふさいだまま
でいるのか、それとも西欧の声を模倣するものまね鳥のままでとどまるのか?」
この論文は、ナショナリズムを基調とするこうした断片を積み重ねることによって構成されているが、その中にアフォリズム的な言語論が挿入されてい
る。フレーブニコフの言語創造の理念は民族の問題と密接に関連しているのだ。そのため、ここでもまずは民族に関する論考を考察し、それと関連づけながら言
語論を検討することにしよう。そうすることで、この論文の断片的でアフォリズム的な言語論も体系的に把握できるようになり、フレーブニコフの理念の全体像
も明らかにできるだろう。
そこでまずは民族に関する論考であるが、フレーブニコフはそれを「海」や「未亡人」といった特異なメタファーを多用することで論述している。この
ことが論文を難解にする要因の一つではあるが、この二つのメタファーはきわめて重要である。まず、「海」というメタファーに関して言えば、それは一度「民
族」と同格で用いられ、また論文の最後には「ぼくたちの原型」と言い換えられている。したがって、これは「民族の原型」といったものを意味するメタファー
であり、イワノフの「民族精神」に対応するような超越的なものであると見なすことができる。問題はもう一方の「未亡人」である。これに関してはまったく言
い換えがなく、その具体的な指示対象を特定できないのだ。ただ、具体的な指示対象は別として、このメタファーはその機能の点において重要である。たとえ
ば、次のような例を見ておこう。
未亡人はその愛撫によって愛しい最初の夫[海]の顔を僕たちに伝えてくれた。気前よく愛撫をくれ、傷を癒す偶像を作ってくれ
たのだ。だから僕たちは臥所を譲ってくれた北方の海の住人であり、その後継者なのだ。
ここには「未亡人」、「海」、そして現代人を表す「僕たち」という三者が現われるが、この三者の関係によって「未亡人」の機能を確認できる。
「海」というのは「民族の原型」を意味するメタファーであったが、「未亡人」はその「海」=「民族の原型」と「僕たち」とを媒介する役割を果たしている。
「未亡人」はその「愛撫」という媒介作用を通して「僕たち」を超越的な民族の原型に触れさせる、何らかの媒体のようなものである。具体的な指示対象はわか
らないものの、それは明らかにイワノフのシンボルと等価な機能を果たしているのだ。もう一つ例を挙げておこう。
もちろん、北方の平原を身にまとった妻[未亡人]は、最初の夫[海]の愛撫を激しく求め、優しい男を受け入れるだろう。そし
てこれによって、女性の魔術的な力によって、その男の顔は、愛しい最初の夫、あの海の顔へと彫刻されていくのではないか? だから僕たちも最初の夫の姿を
なぞるように姿を変え、平原に身を包まれた未亡人の大いなる慈悲に相応しい者となろう。
ここでも「未亡人」は「僕たち」と「海」を媒介している。「未亡人」の愛撫によって、「僕たち」の顔は「海」の顔をなぞるように彫刻され、その姿
を変える。「未亡人」を媒介とすることで、現代人は超越的な「民族の原型」に合わせて自己を作り変え、それと一体化することができるのであり、それによっ
て失われた「民族の原型」を現代に回復することができるのだ。
フレーブニコフがイワノフの精神に従うように思考していることはもはや明らかだろう。イワノフがシンボルを媒介にして超越的な民族精神を回復させ
ようとするのと同様に、フレーブニコフも「未亡人」を媒介として超越的な「民族の原型」を現代に蘇生させようとするのだ。
そして、イワノフとの類似という点では、このメタファーのコノテーションにも注意する必要がある。ここでの「未亡人」とは、「海」=「民族の原
型」の未亡人であり、したがって今は存在しない民族の原型を記憶にとどめる者という意味を含んでいる。フレーブニコフは「未亡人」という特異なメタファー
を用いることで、この媒介者に「記憶」という属性を付与しているのだ。イワノフのシンボルが現代に残された民族精神の遺産であるのと同様に、フレーブニコ
フの「未亡人」も、今は亡き「民族の原型」の未亡人であり、その記憶をとどめる者なのだ。フレーブニコフの言う「未亡人の愛撫」とは、この媒体に残された
記憶を想起する過程であるに他ならない。
したがって、この論考でフレーブニコフが言おうとするのは、現代に残された「未亡人」という媒体の記憶を辿り、それによって現代人が失われた民族
の原型に触れるとともに、それと一体化して超越的な原型を回復させねばならないということであり、ここにはシンボルの記憶を想起して失われた民族精神を回
復しようとするイワノフのシンボリズムと、まったく同一の構図、そしてまったく同一の課題を見いだすことができる。
フレーブニコフの論文の基調をなす民族に関する論考は以上のようなものである。それを確認したうえで、次に言語の問題に移ることにしよう。前にも
言ったとおり、この論文で述べられている言語論はアフォリズム的で断片的である。ただ、それは明らかに上に見たような民族に関する論考と対応するものであ
り、それと関連させれば、フレーブニコフの言語創造の理念を体系的に把握することは可能である。まずは次のような断片を見ておこう。フレーブニコフは「語
根」 ヌ・犱ネ と「言葉」 ヌ魵鏸 を対照させながら、次のように述べている
(23)
。
狡猾なユークリッドたちもロバチェフスキイも、ロシア語の語根を11の不朽の真理と呼びはしないだろうか? 彼らは語根を神
の業、言葉を人間の手による業と呼び、言葉の中に生と死の痕跡を見いだすのだ。
ここでは言葉と語根が二元論的に区分されている。言葉が「生と死の痕跡」を持つ「人間の業」であるのに対し、語根は「不朽の真理」の資格を持つ
「神の業」である。つまり、言葉が生成変化する「現象」に過ぎないのに対し、語根は永遠不変の「本質」なのだ。だが、注意しなくてはならないが、語根は本
質の超越性を分有するとはいえ、本質そのもの、つまり超越的な言語そのものではない。語根は現象である言葉とは区別されつつも、同時にその言葉=現象の中
に埋め込まれているからだ。フレーブニコフにとっての語根とは、生成変化する言葉の中に残された、超越的な原初の言語の痕跡のようなものである。
すでに明らかなように、フレーブニコフにとっての「語根」とは、言語の分野に適用された「未亡人」なのである。超越的な言語そのものはすでに失わ
れているが、その痕跡が「語根」という形で現代にも残されている。したがって、この「語根」に残された記憶を想起すれば、超越的な原型である原初の言語に
遡行することができ、現代の言語をそれと同一化させることで、それを回復させることもできる。そして、この回復すべき超越的な原型こそが、他ならぬ「全ス
ラヴ語」なのである。
そして、虚の疾風がつかみ取ろうとしている色の様々に異なった木の葉、つまりスラヴ系の諸語をつけた木の幹について、また平
らにされ、一つの共通の円環になった渦巻、つまりスラヴ共通の言葉について考えねばならないのではないか?
「スラヴ共通の言葉」という「木の幹」から成育したスラヴ系の諸語は、今や分裂しており(「色の様々に異なった木の葉」)、原初の記憶を喪失して
完全に自立しようとさえしている(「虚の疾風がつかみ取ろうとしている」)。こうした分裂を克服するには、「木の幹」について、すなわちスラヴ諸語の共通
の起源について考えねばならない。フレーブニコフが「語根」に残された記憶を想起することで回復させようとするのは、このように原初の言語として想定され
た「スラヴ共通の言葉」、すなわち超越的な「全スラヴ語」なのである。
フレーブニコフの言語創造の理念とはこのようなものである。日常的に使用される「言葉」は現象であるに過ぎないが、そこに埋め込まれている「語
根」は、原初の言語を記憶するその痕跡である。詩人はそれを言葉の中から取り出し、そこに残された記憶を想起する。それによって超越的な原初の言語、「全
スラヴ語」が回復され、スラヴ諸語の分裂は克服される。
フレーブニコフの言語創造の理念はイワノフのシンボリズムと完全にパラレルである。イワノフが、現代に残された遺産であるシンボルの記憶を想起し
て、失われた民族精神を回復させ、民族の分裂を克服しようとするのだとすれば、フレーブニコフは現代に残された痕跡である語根の記憶を想起して、失われた
スラヴ共通の言葉を回復させ、それに基づいてスラヴ民族の一体性を実現しようとする。両者は、二元論的な思考様式、記憶の想起という方法、超越性に基づく
全体性の回復という課題ムこれらのものを共有している。フレーブニコフはイワノフを通してこうしたシンボリズムの文脈を継承し、その課題を言語の分野で遂
行するようなものとして、自身の言語創造の理念を成立させているのである。
3. フレーブニコフの言語創造と未来派の前衛精神
フレーブニコフはこうした理念に基づいて言語創造の実践を始める。それは、たとえば、有名な作品『笑いの呪文』がそうであるように、同一の語根か
ら派生させた多様な造語によって詩を構成するというような方法で行われた。その最初の数行を引用しよう。
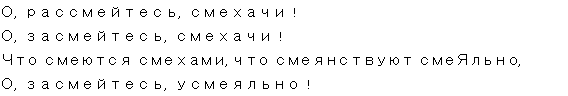 (24)
(24)
ここでは「笑い」を意味する語根 ・
から派生させた多様な造語を用いて詩が構成されている。先に明らかにした言語創造の理念にしたがって言えば、現象である言葉を解体し、そこから取り出した
語根 ・
に基づいて、その記憶を辿るように言語創造が行われているということになる。後にフレーブニコフ自身がこうした初期の試みを総括して言った表現を用いるな
ら、「語根の織りなす円環を断ち切ることなく、あらゆるスラヴの言葉を互いに入れ替えてしまうような魔法の石を見いだすこと、スラヴの言葉を自由に溶け合
わすこと」
(25)
、
こうした試みがなされている。フレーブニコフは造語を用いた詩を創作することで、語根に基づくスラヴ共通の言葉の創造という自らの課題を実践していくの
だ。
しかし、こうしたフレーブニコフの試みはシンボリストに受け入れられることはなく、逆にそれに対抗する未来派に受容されることになる。だが、未来
派の詩人はそれをフレーブニコフ自身の理念に基づいて受容したわけではなかった。最初に述べたように、未来派はカリネスクの言う意味でのモダンの典型であ
り、常に新しさを求めて前進し続ける運動である。彼らはフレーブニコフを受容する際にも、こうした前衛精神を背景にしてフレーブニコフの造語を独自に解釈
し、それを自分たちの文脈に従って読み換え、そうする限りでそれを自らの運動に取り込むことになった。
ここでは未来派の詩人たちがフレーブニコフの造語をどのように受容し、また読み換えたのかを明らかにしながら、それに基づいて未来派独自の文脈、
超越性を回復しようとするシンボリズムとはまったく異質な未来派の前衛精神について検討することにしたい。
3-(1) 未来派による言語創造の受容
フレーブニコフの造語と未来派の運動との関係を考えるため、まずはフレーブニコフが未来派に受容されたときの状況を明らかにしておこう。よく指摘
されるように、未来派の運動を考えるうえでは美術と詩の関連という問題はきわめて重要である
(26)
。それは、絵画の分野でも活躍する詩人がいたという点や、詩人と画家が共同して文集を発
行したというような点においてもそうなのだが、それ以上にここで注目しておきたいのは、未来派の詩人が絵画の実験的な試みに強い関心を示し、それをモデル
として自らの詩を新しい前衛的実験として成型しようとしていたという点である。たとえば、アヴァンギャルドにおける詩と絵画の平行性を記号論的な観点から
研究しているグルィガルは、当時芸術のあらゆる分野で伝統的な表現方法の刷新が求められていたとしたうえで次のように述べている。
まさにそれゆえに、キュビズムの絵画が発見したものは、詩人や彫刻家や劇作家の関心を即座に引きつけた。10年代は絵画のヘ
ゲモニーの時期と見なすことができる。他の芸術の諸ジャンル、特に詩は、絵画の実例にインスピレーションを受け、キュビズムの絵画のいくつかの手法を自ら
に固有の条件のもとで応用しようとしていた。 …… とりわけロシアにおいては、アヴァンギャルドの詩の原理は絵画の発展と密接に結びついていた。
(27)
グルィガルが言うように、ロシアの未来派詩人は絵画の実験に強い関心を向け、それをもとにして自らの詩の原理を成型しようとしていた。マヤコフス
キイが1912年に行った、「もっとも新しいロシアの詩について」と題する講演の要旨からもそのことは伺える。そこには美術と詩に関する次のようなテーゼ
が含まれている。「2)絵画と詩は最初に自らの自由を意識した。3)芸術の真理の把握に向かう、絵画と詩の道程の相似性」
(28)
。マヤコフス
キイは、このように絵画と詩の試みに平行性を見いだしているわけだが、この講演が行われたのは、実はマヤコフスキイが本格的に詩を書きはじめてまだ間もな
い頃のことであった。つまり、このテーゼは事実を述べたものというよりも、実のところ、絵画をモデルとして自己の詩の原理を成型しようとするマヤコフスキ
イの志向、あるいは願望を表したものにすぎなかったのである。
常に「新しさ」を追求する未来派の詩人は、印象主義、フォーヴィズム、キュビズムと急速に展開していく絵画の運動の中に、前衛芸術の模範的な在り
方を見いだしていたのである。だが、彼らが絵画をモデルにしていたということは、逆に言えば、詩の分野にはそれに対応するような新しい試みが欠けていたと
いうことでもある。実際、ダヴィード・ブルリュークは1910年の未来派最初の文集「裁判官の飼育場」に関連して次のように述べている。「これが文学にお
ける革命の始まりだったが、絵画のそれはすでに二年前に始まっていた」
(29)
。絵画においては「すでに二年前」から前衛的な活動が行われていたのに対して、詩の分野
では、この最初の文集が登場するまで、前衛運動という点では実質的な成果がなく、まったくの空白状態だったのである。そのため、当時の未来派詩人は、絵画
に比べて詩が遅れているという意識を持たざるをえなかった。彼らが「新しさ」を至上の価値とするだけに、また同時代の絵画の前衛的な実験がすでに成功して
いただけに、そうならざるをえなかった。フレーブニコフの造語はこのような状況の中で発見された。そのため、それは新しい試みを強く待望する未来派詩人に
は、何よりも詩の遅れを取り戻す「新しい」試みとして、詩における美術の前衛の等価物として立ち現われることになったのだ。
このような事態は、たとえばリーフシツの回想からはっきりと伺える。彼は当時の自身の課題について次のような回想を残している。
1900年代のフランス絵画は他ならぬこの面によって、つまりシンボリストによって袋小路に追い込まれてしまった言葉の領域
に、その革命的なエネルギーや、すでに具体化している最初の諸成果を移し換えうるという可能性によって、他の何よりも私の想像力に働きかけたし、何よりも
私の心に近いものだった。この新しい実験、これらのいまだ組織化されていない技法をいかにしてロシア詩の領域に持ち込むことができるのか、私にはもちろん
わからなかったし、わかるはずもなかったが、光が訪れるとすれば、それはセーヌの川岸から、解放された絵画の幸福な国からでしかないということは堅く信じ
ていた。
(30)
ここには、美術の前衛に対する詩の遅れという詩人の意識がはっきりと現われている。リーフシツもまた絵画の「新しい実験」に注目し、その技法を
「ロシア詩の領域に持ち込むこと」によって自己の詩を成型し、詩の遅れを取り戻そうとしていたのである。だが彼が、その方法は「もちろんわからなかった
し、わかるはずもなかった」と言うように、詩の分野にはやはり彼らの前衛精神に見合うような実質的な成果は欠けていた。こうした状況の中で、リーフシツは
フレーブニコフの造語を発見することになる。
私は「裁判官の飼育場」の詩人[ブルリュークのこと]にフレーブニコフのことを夢中になってたずねた。フレーブニコフの作品
がロシア詩の発展の不可避の道として当時の私の意識に描かれていたものとは極端にかけ離れていたことや、彼の『動物園』や『鶴』が、私には純粋な亜流であ
り、シンボリズムの潮流の最後の反響のように思えたということはまったく問題ではなかった。私にとって彼はもはやクリビンの「印象主義者のスタジオ」につ
い最近現われたばかりの『笑いの呪文』の作者だったのであり、したがってすでに輪郭の出来上がっていた闘争(もっともまだ私の想像の中でのことだが)にお
ける最も信頼しうる同盟者だったのである。
(31)
グルィガルは、キュビズムが新しい転回を求めていた詩人の関心を即座に引きつけたと言っていたが、同じようにフレーブニコフの造語は美術の前衛と
等価な詩の実験を強く求めていた詩人の関心を即座に引きつける。リーフシツは造語を用いた『笑いの呪文』の中に、自分が求めていた詩の実験的な試みを見い
だし、まだ一度も会ったことのないフレーブニコフを、このときすでに自分の「最も信頼しうる同盟者」と見なしてしまう。詩の空白を意識していた未来派詩人
には、フレーブニコフの造語は何よりもその空白を埋める「新しい実験」として現象することになるのだ。
そしてそれとの関連で指摘しておくべきなのは、リーフシツが造語を用いた『笑いの呪文』のみに関心を集中させ、造語を用いていない作品を完全に無
視していることだ。実際、彼はフレーブニコフの他の作品を「ロシア詩の発展の不可避の道」からかけ離れたものと見なし、造語を用いていない『動物園』や
『鶴』を「純粋な亜流」「シンボリズムの潮流の最後の反響」として否定している。リーフシツにとって重要なのはあくまでも造語であり、その他の作品など
「まったく問題ではなかった」のである。リーフシツは他の作品を無視することで、フレーブニコフの造語をあくまでも前衛的な実験として表象しようとする。
詩の前衛運動を強く求めていたリーフシツは、言語創造という試みの中に自らの願望の充足を読み込んでしまうのであり、そうしたイメージに合致しない要素は
あらかじめ排除してしまうのだ。
これと似たようなことは、これよりも前にフレーブニコフを発見したブルリュークについても言える。彼は後に未来派の文集「社会の趣味への平手打
ち」に掲載された「キュビズム」と題する論文で、詩においてキュビズムに対応するような試みを行っているのはフレーブニコフだけだと述べているが
(32)
、彼がフレー
ブニコフを発見し、彼に強い関心を示したのも、やはりその造語のためだった。マチューシンの回想によれば、ブルリュークは当時、「芸術の新たな動向の発展
に貢献しうる勢力を、驚くべき正確な嗅覚を働かせて自分のまわりに結集させていた」のだが、カメンスキイから言語創造による作品を創作している詩人がいる
という話を聞き、強い関心を示す
(33)
。
ブルリュークはフレーブニコフの作品を読んでいたわけではないが、言語創造によって作品を構成するという事実そのものが「芸術の新たな動向の発展に貢献し
うる」試みとして、彼の関心を無条件に引きつけてしまうのだ。ブルリュークもまた、造語によって詩を構成するという事実に基づいて、フレーブニコフのイ
メージを観念的に構成してしまうのである。
フレーブニコフはこのようにして未来派の詩人に発見された。二つの例に見られるように、当時未来派の詩人たちは美術の前衛を意識し、それとの対比
で詩の遅れを強く意識せざるをえなかったのだが、その空白を埋める新しい試みを他ならぬフレーブニコフの造語のうちに見いだしてしまうのだ。しかもそのと
き、フレーブニコフの言語創造の理念や彼の実際の作品は、ほとんど視野の外に置かれ、造語を用いて詩を構成するという方法のみが彼らの関心を引きつけ、彼
らはそれをもとにフレーブニコフのイメージを構成してしまう。こうして彼らはフレーブニコフの造語に前衛的な実験というイメージを投影し、そのかぎりでそ
れを自らの運動に取り込んだのだった。フレーブニコフの言語創造の試みは、この時点ですでに背景にあるシンボリズムの理念からは切り離されているのだ
(34)
。
3-(2) 未来派の前衛精神と超越性の消去
フレーブニコフの造語はこのようにして未来派の運動に受容され、その活動を構成する重要な手法の一つとなっていくわけだが、当然のことながら、そ
れによって言語創造にはフレーブニコフ自身が与えたのとは別の課題が与えられることになる。フレーブニコフの造語はその本来の理念から切り離されるだけで
はなく、未来派の前衛運動を実現する実験的な試みとして、それに適合した新たな意味づけを与えられるのだ。次に、未来派の詩人たちがフレーブニコフの造語
をどのように読み換えたのかを明らかにしながら、その読み換えの背景にある未来派独自の文脈について考察することにしよう。
未来派の中でフレーブニコフとともに言語の問題を自己の課題の中心に据えていたのはクルチョーヌィフである。彼はいくつかの論文で造語の方法をラ
ジカルに展開させた超意味言語「ザーウミ」の理論を展開し、さらには彼のザーウミの理論は後に「41°」や「ザウームニキ」といったグループにひきつが
れ、ロシア詩の前衛運動における一つの重要な系譜を形成することになる。だが、ここではこうした展開を追うことはしない
(35)
。ここで興味
があるのは言語実験の歴史ではなく、そもそもの初め、未来派詩人がフレーブニコフの造語を「新しい実験」として受容したとき、それをどのように理解し、そ
れにどのような意味づけを与えたのかということである。後の展開においては、たとえばクルチョーヌィフの個人的な傾向という要素も含まれてくるが、最初の
段階での読み換えには未来派固有の文脈がそのまま反映していると考えられるからである。
そうした点を明らかにするうえで参考になるのは、未来派の最初のマニフェスト「社会の趣味への平手打ち」に載せられている造語の理論である。とい
うのは、これはマルコフが指摘していることだが、このマニフェストが作成される前に実際に造語を行っていたのはフレーブニコフだけだったのであり
(36)
、したがっ
て、ここで述べられている理論は、他ならぬフレーブニコフの造語をモデルとして形成された理論であることになるからだ。われわれはこの理論から、未来派の
詩人がフレーブニコフの造語をどのように理解し、どのような意味づけを与えることでそれを前衛的実験と見なしたのかを知ることができる。それは未来派の活
動プログラムとして次のように述べられている。
われわれは以下のような詩人の権利を尊ぶことを命令する。
1.自由に派生した言葉で詩人の辞書の語彙を増大させること(新機軸としての言葉)。
2.既成の言語を徹底的に憎悪すること。
…
(37)
この宣言のうち特に最初の宣言がフレーブニコフの理念とはまったく異質である。フレーブニコフが造語によって行おうとしたのは、現象である言葉を
解体し、語根を媒介として本質である超越的な原初の言語を回復することであった。つまり、問題は現象から本質へ向かうことにあった。ところがここで宣言さ
れているのは、造語によって言葉を自由に派生させること、つまり現象である言葉から出発してさらにその現象を量的に拡大していくことである。フレーブニコ
フが垂直方向に現象から本質に向かうのに対して、未来派はそれとはまったく逆に、水平方向に現象の量を拡大していくことを求めるのである。
先にも言ったように、この未来派の理論は他ならぬフレーブニコフの造語をモデルとして形成された理論である。未来派の詩人は、フレーブニコフの造
語を彼ら自身の文脈に従って解釈し、それを自分たちの活動プログラムとして定式化したわけだが、結果としてそれはもとのフレーブニコフの理念とは正反対の
方向に向かうことになったのだ。では、なぜこのようなことが生じたのか。それは言うまでもなく、フレーブニコフが言語創造の理念を成立させた文脈と、未来
派がその実践を解釈した文脈がまったく異なっていたからだ。フレーブニコフの理念がシンボリズムの文脈を継承して成立したものだとすれば、未来派の詩人は
それをまったく異質な彼ら自身の文脈に置きかえ、その中で造語を独自に解釈したのである。
では、シンボリズムとは異なる未来派独自の文脈とはいかなるものか。それはフレーブニコフと未来派、それぞれの造語の理論の差異の内にはっきりと
読み取ることができる。フレーブニコフが現象から本質へ向かうのに対して、未来派の詩人は現象から出発してさらに現象の量を拡大する方向へ向かう。つま
り、未来派の理論の内にはフレーブニコフの理念には存在していた本質への志向が、すなわち超越的なものへの志向が欠けているのだ。未来派の詩人は言語創造
を、新しい現象=新しい言葉を不断に産み出す生産技術として読み換えたわけだが、それは彼らがフレーブニコフの造語に存在していた超越的なものへの志向を
見落としたか、あるいは排除したことの結果である。このことにも示されているとおり、未来派の詩人はシンボリストとはまったく逆に、超越的なものを一切認
めようとはしない。シンボリズムが現象と本質の二元論を特徴とするのに対して、未来派は超越性を排した、現象のみの一元論をその特徴としているのだ。以下
の部分では、この一元論という特徴、及びそこから生じる未来派の諸傾向について考察を進めていくことにしよう。
未来派の詩人が一元論的に思考していたことは、たとえばマヤコフスキイのアーバニズムに見て取ることができる。マヤコフスキイは、未来派の詩は現
代都市の詩であるとしたうえで、次のように述べている。「電話、飛行機、エレベーター、輪転機、舗装道路、工場の煙突、コンクリートの集合住宅、煤や煙、
こうしたものが新しい都会的自然の美の要素である」
(38)
。
シンボリストが可視的・経験的な現実の背後に不可視の超越的な世界が存在するものと見なし、現象を低次の現実として扱うのに対し、マヤコフスキイは都市の
さまざまな事物を低次の現実としてではなく、それ自体で価値を持つものと見なしている。マヤコフスキイにとっては、経験的な現象こそが「美の要素」なので
ある。そして、さらに重要なのは、このように価値の中心が本質から現象に移行するのにともなって、時間意識もシンボリズムの場合とは正反対になっているこ
とだ。
だが最も重要なのは、生活のリズムが変化したことだ。すべてのものが映画のフィルムで見るように、高速で、束の間に過ぎ行く
ものとなった。流れるような、穏やかでのんびりした古い詩のリズムは現代の都市生活者の心理には合致しない。熱狂的興奮、それが現代のテンポを象徴するも
のだ。
(39)
シンボリズムが本質のもとで現象を否定するのは、本質が時間を超越した永遠性を有するのに対し、現象は一時的で、束の間のものでしかないからであ
る。シンボリズムにとっては生成変化する現象の背後にある、永遠の本質こそが価値を有するのだ。これに対して未来派は、彼らが超越性を一切認めない以上、
時間を超越した永遠の価値といったものを認めず、現象の属性である束の間の時間的性質を積極的に肯定する。「映画のフィルムで見るように、高速で、束の間
に過ぎ行くもの」にこそ価値があるのだ。シンボリズムの文脈を継承したフレーブニコフが語根を「不朽の真理」として重視し、言葉を「生と死の痕跡」を持つ
ものとして否定していたのに対して、未来派がそれを逆転させ、常に生成変化し続ける言葉の方を重視し、それを不断に生産していくことを自己の課題としてい
るのもこの時間意識の差異に適合しているといえるだろう。
そしてさらにいえば、未来派の場合、このような時間意識は都市の事物といった芸術の対象だけではなく、芸術そのものにも向けられることになる。彼
らにとっては芸術も永遠の価値を持つものではなく、常に変化し続ける一時的で束の間の現象にすぎないのである。たとえば、マルコフの指摘によれば、ブル
リュークは1912年の公開討論会で次のような講演を行っている。「今回、ブルリュークは『美と芸術の進化』について講演した。彼は、芸術におけるあらゆ
る真理の寿命は25年であり、したがっていかなる美の概念も相対的で一時的であると主張した」
(40)
。超越性を一切認めない未来派にとっては、芸術といえども現象にすぎないのであり、それ
もやはり一時的で束の間の価値しか持ちえないのである。
未来派の運動が常に「新しさ」を追求し続ける前衛精神を特徴にすることはこれまで何度も指摘してきたが、彼らのそうした傾向も実はこのような相対
主義的な芸術史観にその根拠を持っている。ブルリュークが言うように、あらゆる価値が一時的で常に変化し続けるとするなら、唯一特権的な価値を持つのは、
このような変化の最先端に居続けること、常に新しい現象を開拓し続けることでしかない。いかなる価値も超越性に支えられておらず、すべてが相対的である以
上、生成変化し続ける芸術現象の中では、もっとも新しくオリジナルなもののみが、唯一差異化された価値を獲得できるのだ。「新しい」という言葉が未来派詩
人に多用されるのはこのためである。
ところで、最初に未来派の前衛精神は、グロイスやクリツィンの定義するような超越性の回復を試みる運動というアヴァンギャルドの概念には妥当せ
ず、むしろ超越性を徹底して排除しようとするものであると指摘しておいた。それは上に見たように、未来派の詩人が生活の領域だけではなく、芸術という美的
なものの領域からも超越性を排除しようとするからだ。美的なものの領域は、近代の市民社会においては生活の他の領域とは異なる特殊な意味を帯びていたので
ある。たとえば、ハーバーマスは言う。「芸術とは、市民社会の物質的な生活過程のなかではいわば違法なものになっている、あのさまざまな欲求の充足ムたと
えそれが潜在的な充足にすぎないにせよムのための留保地とでもいうべきものである」。芸術とは「市民的合理化の犠牲に対してその補完的な迎撃地点となる」
ものであった
(41)
。
近代の市民社会においては、芸術は合理化の過程で消失していく諸価値を保存するような特殊な領域と見なされてきたのである。もちろんこうした価値には様々
なものがありうるだろうが、生成変化し続ける物質的な生活過程に対する、永遠不変に妥当する超越的な精神領域という価値もそこに含まれることは間違いな
い。未来派の超越性の排除が徹底しているのは、彼らが生活の領域だけではなく、特殊領域としての美の領域においても永遠性という価値を否定するからであ
る。マヤコフスキイは言う。
ほとんど100年もの長きにわたって、同じような生活をしてきた作家たちが、同じような言葉を発してきた。美の概念は成長が
止まり、生活から遊離し、自らを永遠で不死であると宣言してきた。
(42)
マヤコフスキイにとっては、美的な領域を生活の領域から切り離し、それを永遠不変のものとして特殊化することは単なる虚偽にすぎない。美的なもの
は永遠でも不死でもなく、それは物質的な生活過程の諸現象と同様に、「成長」しなくてはならないのだ。シンボリズムが芸術という特殊領域に残存する超越性
を社会全体に回復しようとする点でラジカルであるとすれば、未来派の場合には芸術という特殊領域からも超越性を追放しようとする点でラジカルなのである。
超越性の回復というグロイスやクリツィンの定義は、未来派の前衛精神には妥当しない。未来派は超越性を回復しようとするのではなく、むしろ徹底してそれを
排除しようとするのである。
未来派が美の領域からも超越性を排除し、すべての芸術を生成変化する相対的なものと見なし、「新しさ」という価値のみを唯一特権的な価値としてい
たことを考えるなら、彼らがフレーブニコフの造語を、現象である言葉を不断に生産するようなものとして読み換えたことも当然のことだと言えるだろう。新し
いものだけが価値を持つ以上、彼らは不断に新しい現象を開拓していかねばならないのであり、造語という方法も一回的に何らかの不変の言語を創造するような
ものではなく、常に新しい現象=新しい言葉を派生させ続けるような方法でなければならないのである。マヤコフスキイはフレーブニコフの造語に関して次のよ
うに述べている。
もし、 ≪железовут≫
という言葉があなたには説得力がないように思われるなら、それを捨てればいい。複雑に縺れあった感覚をより明瞭に表現するような新しい言葉を考え出せばい
い。私にとってフレーブニコフの例が貴重なのは、到達点としてではなく、一過程としてなのである。
(43)
フレーブニコフは不変の超越的な起源として「全スラヴ語」を再構築しようとしたのであり、それは生成変化する諸言語とは区別される、絶対的な永遠
の言語でなければならなかった。しかし、マヤコフスキイにとっては、言葉はそのような自己同一的な「到達点」に留まるものであってはならない。それはあく
までも「一過程」にすぎないのであって、詩人は造語という方法を用いて不断に新たな言葉を生産し続けねばならないのだ。未来派の詩人がフレーブニコフの造
語を自らの運動に取り込んだのは、このようにそれを新しい言葉を不断に生産する技術として読み換え、自らの文脈に適合するものとして理解したかぎりでのこ
とだったのである。
3-(3) 補遺
未来派独自の文脈とはこのようなものだが、もはや明らかなように、フレーブニコフと未来派の間にははっきりとした差異がある。本論文の目的はこの
差異ム一元論と二元論、及びそこから派生する両者の相反する諸傾向ムを明かにすることにあったのだが、そのことを明かにした以上、当然次のような疑問が生
じてくるだろう。つまり、このように異質な傾向を持つフレーブニコフと未来派がこれ以降いかにして同一の運動の内に共存しえたのか、両者のいずれか、ある
いは双方が運動の展開する中で変質し、差異が解消されていったのではないかというようなことだ。ここではもはやこうした問題に詳細に答える余裕はない。た
だ、こうした差異は潜在的にではあるが、これ以降も常に存在し続け、両者はこうした差異を抱えたまま一つの運動のうちに共存していたということはできる。
というのも、この差異はこのあと未来派の運動が展開し、それが全盛期に入ったころ、一度だけはっきりと表面化することになるからだ。それは1914年、イ
タリア未来派の中心人物、マリネッティがロシアを訪問したときのことである
(44)
。このときロシアの未来派の内部にはマリネッティに対する二つの異なった対応が見られる
のだが、その二つの対応の違いは、それを理論的につきつめていくと、これまで見てきたようなフレーブニコフと未来派の差異とつながっているのだ。ここでは
それを簡単に確認しておこう。
二つの対応の内の一つは、フレーブニコフ、および彼を支持するリーフシツが示したものである。彼らはマリネッティを徹底的に拒絶するのだが、その
際「東と西」あるいは「アジアとヨーロッパ」という構図を用いる
(45)
。彼らにとっての「東と西」は、単なる空間的な対立ではなく、東は来たるべき未来とし
て、西は超克されるべき過去として表象される
(46)
。
彼らがイタリア未来派を拒絶するのは、それが西=過去に属するものである以上、表面的な新しさを求めることはできても、世界を決定的に変革するような能力
は持たず
(47)
、
むしろ真の変革を阻害する要因となりうるからだ。そのような真の変革は、フレーブニコフの言葉でいえば、「ヨーロッパの半島的な悟性」を克服し、アジアの
「大陸的な知性」を実現することによってしか可能にならない
(48)
。フレーブニコフの自己表象はかつての「スラヴ」から「アジア」に変わっているが、その
ことは問題ではない。フレーブニコフにとって重要なのは、「スラヴ」にせよ、「アジア」にせよ、「西欧」の「悟性」のヘゲモニーによって抑圧されている自
己の同一性を解放し、それに基づいて世界を再編すること、スラヴの、あるいはアジアの本質を実現することで世界を決定的に変革することなのだ。超越的な本
質の存在を想定し、それを回復することで世界を再編しようとすること、こうした点でフレーブニコフの態度は1910年前後から一貫している。
一方これと正反対の反応を示したのはマヤコフスキイであった。彼は「詩の中二階」派の詩人とともに次のようなマニフェストを公表した
(49)
。「…我々は
イタリア未来派とのあらゆる影響関係は否定するが、文学的な平行関係は指摘するものである。未来主義とは巨大都市が産み出した社会的潮流であり、それ自体
があらゆる国家的な差異を駆逐してしまうのだ。未来の詩とはコスモポリタンなのである…」。マヤコフスキイのこうした態度も彼の一元論的な思考から必然的
に要請されるものであり、やはり一貫している。超越的なものを一切認めない以上、マヤコフスキイはいかなるものであれ、歴史を超越した本質主義的な自己同
一性など認めるわけにはいかない。マヤコフスキイにとっては、ロシア的、あるいはアジア的本質など虚構にすぎないのだ。マヤコフスキイの「コスモポリタ
ン」という自己表象はフレーブニコフのそれと明確な対照をなしている。
またフレーブニコフがアジアの自己確立という主体の変革を通して世界を再編しようとするのに対して、マヤコフスキイが都市化という外的な客体の物
質的な進歩に準拠を置いていることも対照的である。フレーブニコフの変革は一回的に行われる絶対的なものであるのに対し、マヤコフスキイの変革は物質的な
世界が常に変化していく以上、それに準じて永続性を要請するものである。ここにも二元論に基づいて永遠を志向する時間意識と、一元論に基づいて不断の前進
を志向する時間意識の差異がはっきりと現われている。
このように、1910年前後、フレーブニコフが未来派に受容されたときに存在していた両者の異質性は1914年の時点でも存在し続けている。この
間、両者の差異ははっきりとした形で現われることはなかったが、それは解消したわけではなく、単に潜在化していただけなのだ。そしてマリネッティの訪問と
ともにこうした対立が表面化した後も、多少の変化は認められるものの、未来派が分裂するという事態には至らず、未来派の運動はそれ以前と同じような状態で
続いていくことになる。ロシアの未来派は強い求心力を持つ一体化した運動に見えるが、実際にはそれはまったく相入れないような二つの傾向を内包する複合的
で不安定な運動体だったのである。
4. まとめ - モダニズム芸術と社会 -
フレーブニコフの言語創造の理念の成立と受容の過程を追いながら、シンボリズムと未来派というロシア・モダニズムの二つの傾向について考察してき
た。フレーブニコフの造語の試みは、前衛的な実験でもないし、新しい言葉を不断に生産するような方法でもない。未来派の言説空間の中に置かれると、彼の試
みはそのようなものとして現象せざるをえないのだが、少なくとも、その初期の試みは、シンボリズムの課題を言語の領域において忠実に遂行しようとするもの
であり、未来派の前衛精神とはまったく異質なものであった
(50)
。
そのシンボリズムと未来派の異質性に関しては、超越性という観点から検討し、一方がそれを回復しようとする運動であり、他方がそれを徹底して消去
しようとする運動であることを明らかにした。未来派が超越性を徹底して消去しようとし、芸術という特殊領域に残存する超越性をも排除しようとしたのだとす
れば、シンボリズムは逆に、芸術の領域に保存されている超越性を芸術という特殊領域を越えて社会全体に適用しようとしたのだといえるだろう。そして、その
ことを考えるなら、両者が異なった方向性においてではあるが、同じ事態に対する反応として形成された運動であったと考えることも不可能ではない。同一の事
態とは、クリツィンの言う「神の死」という事態であり、言い換えるなら、テクノロジーによる調和の破壊、社会の細分化や合理化といったものになるだろう。
シンボリズムにせよ、未来派にせよ、そうした社会の変質に比例して先鋭化する芸術の領域の特殊性を、つまり美の領域のみが社会と対抗するような価値に支え
られていることを、おそらくは痛烈に意識せざるを得なかったのである。こうした意識のもとで、一方が美の領域の特殊性に可能性を見いだし、そこに残存する
価値を原理として社会に調和を取り戻そうとしたのだとすれば、もう一方は美の領域の特殊性を排除し、芸術と社会の間の溝を埋めようとしたのだと言える。シ
ンボリズムと未来派の異質性を強調するだけではなく、このような両者に共通の基盤を解明する作業も重要であるが、この点に関しては今後の課題とし、稿を改
めて論じることにしたい。
45号の目次へ戻る
(24)
(24)