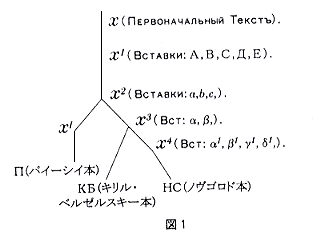
三 浦 清 美
Copyright (c) 1997 by
the Slavic Research Center( English
/ Japanese ) All rights reserved.
| はじめに |
写本一覧 |
このテキストについて |
凡例 |
テキストと試訳 |
テキスト解題 |
研究史と研究課題 |
注釈 |
付録 |
要 約 |
本稿の課題は、15世紀の写本文集『ズラタヤ・マチッツァ(金の梁)Златая
Матица』に収容されたテキスト『聖グリゴーリイ講話』の翻刻と、その生成過程をめぐる考察である。本研究は1992年9月から
1993年12月まで筆者がサンクト・ペテルブルグ大学に研究生として在籍し、その間に行なった調査がもとになっている。調査研究の内容は1994年東京
大学に提出した博士論文の第二章としてまとめられたが、本稿はさらにその後の調査(1996年8月)結果を盛り込み、若干の訂正を施した最新の研究成果で
ある。
本論考は、テキスト学 текстология
と呼ばれるスラヴ文献学の有力な一研究分野に属する。
従来資料入手の制約などから、日本においては特別な関心が払われてこなかったが、研究資料の淵源を見極め、他のあらゆる研究の基礎を創るという点で、テ
キスト学は極めて大きな意義を持っている。テキスト学とは、あるテキスト(作品)につき、種々の写本に集められた様々なヴァリエーションを集め、それらの
異同に一字一句厳密な検討を加え、写本に含まれる情報(写本成立年代・場所・状況、保管者、保管場所など)、テキストに含まれる情報(執筆者、執筆年代・
場所・状況)、方言などの言語的特徴、テキストの叙述構成など、その他あらゆる要素を比較検討総合したうえでヴァリエーション相互の影響関係を確定し、信
頼に足る刊行テキストを作成する仕事である。
上記のように、テキスト学は最も基礎的な仕事であるがゆえに、一見単純な作業の連続に見えるが、内実それには、東西キリスト教会の基本文献や略号を多用
する写本表記の煩瑣な規則に精通することはもとより、写本や作品の成立を促した歴史的状況への洞察や中世人の世界観への想像力豊かなアプローチが要請され
る。テキスト学は研究者の総合的な実力が最も鋭く問われる分野なのである。
テキストの具体的な手続きに関しては、個々のケースに即して考えることが不可欠であり、限られた紙面で説明を施すことは本来不可能である。また、中世ロ
シア文献の学としてのテキスト研究の経験を集大成したリハチョフによる大著
*1
も
別に存在している。考察の過程で疑問が生じた際、あるいは、テキスト学が何たるかを知ろうとするときには、この書を参照すべきことは言うまでもない。本稿
の筆者には方法論について詳述する責は重すぎるのであるが、手続きについて最も基本的な事柄を次に略述したい。
まず、最初の段階はウォーター・マークによる写本成立年代の確定である。この確定方法については本文(ただし、『後篇』)に述べた。写本の成立年代の順
は必ずしもテキストの成立年代の順と一致せず、新しい写本に古いテキストが残存するケースも十分に考えられる。しかしながら、テキストの成立年代が写本の
成立年代よりも新しいことは当然ながらありえないので、テキストの成立年代を考えるうえで写本の成立年代は一つの指標となりうる。
次に行なうべき作業は、テキストの各ヴァリエーションの字句を比較検討することにより、テキストをオリジナル部分と挿入部分に分け、さらに、挿入部分を
出来るだけ細かくグループ分けすることである。一概にはいえないが、テキストを構成する層の解析の結果、挿入が何段階にわたって行なわれたかがわかること
が多い。
写本成立年代・場所・状況、写本の保管者・保管場所、テキストの執筆者、執筆年代・場所・状況、方言などの言語的特徴、テキストの叙述構成、そして、何
よりもその内容など、あらゆる要素の検討を行いながら、最終的にテキスト生成のプロセスを明らかにしてゆくのが研究の最も重要な段階である。テキストの成
立過程がある程度明らかになり、テキストの各ヴァリエーション間の影響関係が確かめられたならば、次に、それが写本レベルでも確認されるかどうかを調べな
くてはならない。写本間で複数の作品が共有されていれば、写本レベルで影響関係があった可能性が高い。写本レベルでの関与が証明できないならば、両テキス
トの間に第三の写本が介在したことを想定すべきである。現存しないが想定しうる写本・テキストの存在も含めて、テキスト伝承関係の見取り図を系統樹として
示すことがテキスト伝承史研究の最終的な課題である。
以上に述べた手続きは極めて概略的なものに過ぎず、対象とするテキストの性格によってさらに綿密な考察が要求される。
テキスト学は、自然科学の研究に準えれば、応用研究に対する基礎研究にあたると言えるであろう。様々な研究条件が整いつつある今だからこそ、一研究者と
して基礎研究の成果を問うことを志す日本人研究者が現われてもよいのではないかと思う。行き届かない点も多々あろうが、本稿がその試行錯誤の試みの一歩と
なればと、筆者は念願して止まない。『聖グレゴリオス講話』伝承史のテキスト学的研究(前編)
最後に、本論考の構成について触れておきたい。
本稿は二部構成である。紙面の関係上、本紀要に掲載されているものは前半部分『資料篇』のみである。この前半部では、『聖グレゴリオス講話』プスコフ・
ヴァリアントのテキストの確定を主眼として、伝承史をめぐる考察のための資料の提示が行なわれている。より具体的に掲載稿の課題を述べると、1)写本から
テキストを翻刻する、2)試訳を付す、3)現存するヴァリエーションを紹介する、4)本テキストと原典作者との関係を明らかにする、5)本テキストの特徴
を概括する、6)テキスト伝承史を記述する準備作業として研究史を概括する、以上である。
後半部において、私達は様々なヴァリエーションがいかに伝承されてきたかという問題に取り組むことになるが、こちらの方は電気通信大学紀要第9巻2号
(平成9年刊行予定)に『理論篇』として掲載される予定である。論文の分量の関係上変則的な掲載となったことを読者諸賢にお詫びすると同時に、『スラヴ研
究』編集部のご理解に感謝を表する次第である。
テキストの内容に関するコメンタリーは重要な仕事であり、中世ロシアの民衆文化を大きく視野にいれて現在仕事を進行させているが、紙面の都合のため本研
究中にはほとんど反映されていない。なお、本テキストのコメンタリーの一部をなすものとしてまとめた“ロードとロジャニツァ”という神格に関する論文
*2
は『ロシア民話研究』
4号(1996年刊)に掲載されている。
| 1) | パイーシイ文集(Паисиев Сборник)キ リル・ベロゼルスキー修道院写本コレクション(Собрание Кириллобелозкрского монастыря)写本整理番号No. 4/1081 14世紀 第40葉表から第43葉裏ま で |
| 2) | ノヴゴロド・ソフィア・コレクション(Новгодское Софийское собрание)写本整理番号1285番 15世紀 第84葉裏から第87葉表まで |
| 3) | キリル・ベロゼルスキー修道院写本コレクション 写本整理番号 No. 43/1120 第128葉裏から130葉表まで 16世 紀 |
| 4) | НСРК 1946г. 写本整理番号 35/2F.文集『ズラタヤ・マチッツァ 金の梁)』(Сборник "Златая Матица")第145葉目表から第148葉目表まで |
| 5) | チュードフ修道院古写本コレクション(Чудовское
собрание)写本整理番号No.270 第221葉表から第224葉表まで 5)が国立歴史博物館(在モスクワ)に所蔵されているほかはすべて現在シチェドリン名称ロシ ア国立図書館(在サンクト・ペテルブルグ)が所蔵して いる。 |
テキスト:ロシア共和国サンクト・ペテルブルグ市ロシア国立図書館所蔵写本整理番号 НСРК 1946г.35/2F.文集『ザラタヤ・マチッツァ(金の梁)』145葉目 表から148葉目表まで
本テキストは上記の写本から転写を行ない、パンクチュエーション、文法的な整合性などを考慮したうえで、その確定を行なったものである。対照テキ ストとして使用したのは以下のもの。本文中に番号を打ってその異同を示した。
対照テキスト:ロシア共和国モスクワ市国立歴史博物館所蔵 写本整理番号 チュードフ修道院古写本コレクションNo. 270 221葉表から 224葉表まで
| 1 | 本文中単独の番号は、番号をふった НСРК 中のその単語がチュードフ・コレクションでは脚注の単語であることを意味する。 |
| 2 | 本文中同一の番号が二つ出てくる場合、即ち、
|
| 3 | 脚注“ДОБ”の印は НСРК 写本にない表現がチュードフ・コレクション写本に存在することを示す。例え
ば、本文中же
|
| 4 | 脚注“НЕТ”の印は НСРК
写本にある表現がチュードフ・コレクション写本には存在しないことを示す。例えば、本文中
|
| 5 | テキスト中、下点線はパイーシイ写本テキストと同じ箇所、下波線は基本的にパイーシイ本テキストと同じだが目に見える変更をこうむっ た箇所、下実線はパイーシイ本にはないがノヴゴロド本にある箇所、二重傍線は『聖金口イオアネス講話』からの引用。 |
本研究でテキスト翻刻の対象となったテキストは『聖グレゴリオス講話』のプスコフ・ヴァリアントである。本稿でテキストの表題とした『聖グレゴリ オス講話』は便宜上の略称であり、正式には『その注釈に見いだされる聖グレゴリオスの説教 最初の異教徒たちが偶像を崇拝し、これに供物を捧げおりたるの みならず、今もこれを行ないたること』という長い題名がついている。
その題名に冠せられた聖グレゴリオスとは、言うまでもなく、カッパドキア三教父の一人(ほかに大バシレオス、ニュッサのグレゴリオス)、キリスト
教典礼、特に三位一体の教義の確立に力を尽くした聖グレゴリオス・ナジアンゾス・テオロゴスである。カッパドキア南西部のナジアンゾスの司教を父に持つ彼
は、パレスチナのカイサレア、アレクサンドリア、アテナで哲学と弁論術を学んだのち洗礼を受けた。子の神性を認めないエウノミオス派や聖霊の神性を認めな
いマケドニオス派に対して、一貫してニケーア信条の立場を擁護し、コンチタンチノポリス公会議を主導する役割を果たした。彼に冠される「テオロゴス」とい
う名前は、三位一体を観想した者、その教義の確立に寄与した碩学を指す尊称である
鋭い弁証法的議論と流麗な聖書の引用を交えて雄弁に三位一体を擁護した第27-31番講話は『神学講話』とも呼ばれ、その代表的作品として有名で あるが、そのほかにも、244通に及ぶ『書簡集』、400篇が現存する『詩集』、司教の職務から教会の祝日や葬儀などの機会に行なった都合45篇の『講 話』がある。本研究の対象となるテキストの原典とおぼしき作品も、上記45篇の『講話』中39番目に見いだされる。『主顕節の聖なる光の中で』がそれであ る。
『講話』のうちかなりの部分が聖グレゴリオスのコンスタンチノープル司教在任期(379年から381年まで)に書かれているが、この『第39講話
主顕節の聖なる光の中で』も彼のコンスタンチノープル時代の所産で381年1月6日
原典、即ち聖グレゴリオスの『第39講話』の中で、中世ロシアに移植された『聖グリゴーリイ講話』と重なり合う部分はその四分の一に過ぎず、しか もギリシア神話の様々なモチーフが列挙され、取るに足らないものとして退けられる箇所のみであり、講話の主題そのものとは直接関係がない。実は、中世ロシ ア版ではどのヴァリエーションでもそもそも主顕節についてさえ触れられることがないのである。しかも、取り上げられたギリシア神話のモチーフは中世ロシア 版ではことごとく曲解されていると言っても過言ではない。
原典が『第39講話』であることを確認したのは19世紀後半のスラヴィストたちであるが、今一度その原典との突き合わせを行なってみると、原典と 中世ロシア版テキストの間に内容的な符合はほとんどないことがわかる。影響関係の痕跡を見つけることさえ難しい。
つまり、両者を比較すれば、即座に次のような事実が浮かび上がってくるのである。千年にわたるテキスト伝承の過程にはいずこかに大きな断絶があり (どこに断絶があったかは後に触れる)、聖グレゴリオスの手になる原テキストは著しい改変を被り、私達のテキストの中にかれの精神活動の痕跡を認めるのが 極めて難しくなった。このことは次のように言い直すことができよう。様々な時代に様々な地域で筆写を行なった人々が、キリストへの信仰を暖め続ける過程で 兆した様々な問題をこのテキストに投影し続けた結果、それは独自の護教意識に裏打ちされた別個の新しい作品として新たな誕生を見たのである。
逆に、中世ロシア版『聖グレゴリオス講話』の側から見れば、次のようにも言えるであろう。グリゴーリイ・ボゴスロフという名はキリスト教典礼の確 立に力をつくした大権威という意味しか持っていない。実際の作者は、このテキストがプスコフに至るまで遍歴を続けた各々の地で筆写を行なった写字生であ り、かれらが土地の異教的な風習をテキストの中に書き加え、論難の対象とした結果、その誤解や理解不足によってテキストの内容はますます聖グレゴリオスの 原典から遠ざかり、注意深く読んでも意味を解しかねる箇所さえ出てきたのである。
こうした挿入や誤解などによるテキストの変容は、『グレゴリオス講話』というテキストの重要な特徴なので、具体的な例を以下に引用しながら検討を 行なってゆきたいと思う。
『聖グレゴリオス講話』に質的な変化を強いたテキストの改変の典型的な例として、第一に挙げることが出来るのは、“イスラム”や“ヴィール(ある いはヴィーラ)”に関する記述である。
ヴィーラと言えば南スラヴの妖精を指すのが普通である。ヴィーラは、髪を振り乱し、翼を持ち、魔法の衣装をまとう若い女性の姿をしているとされる が、ここでは次のように書かれている。「予言者ダニールがハビロンで殺した蛇をヴィーラと名付けている。」若い女性の姿形をとった妖精は『講話』の作者に よって「預言者ダニールがバビロンで殺した蛇」と捉えられている。これは誤解としてもあまりに不自然であるといえないだろうか。
実はこの記述には写字生たちによる混同が幾重にも隠されているのである。
テキストには預言者ダニエルの名前が現われている。まず、このあたりから探っていってみよう。ダニエルに関する外典物語群の中にダニエルが知恵に
よって異教神ベルと竜を打ち砕く話がある
食欲が旺盛だ(捧げものをすると食物が消える)という理由でベル神が生きた神であると主張するペルシア王キュロスに対して、ダニエルは「あれは内 側は粘土で、外側は青銅でできていて、飲み食いするわけがございません」と答える。王はダニエルの言うことが正しいかどうかを試す。ダニエルが正しければ ベル神の司祭たちが、ダニエルが自分の言明の正しさを証明できなければダニエルが死を賜ることになる。ダニエルは神殿に灰をまき、夜司祭たちと家族が忍び 込んで捧げものを食べていることを暴く。ベル神の司祭たちは家族もろとも殺され、ベル神の神殿はこぼたれる。
また、あるときダニエルは王にバビロニア人たちが崇めている竜をなぜ神と認めぬかを問われる。かれは一笑に付し、「剣も棍棒も用いずに」竜を殺す ことを王に約束する。ダニエルは「ピッチと油脂と毛髪を取り、一緒に煮てだんごを作り、竜の口に入れた。竜はそれを飲み込むや否や体が裂けた。」
以上二つの話は、ダニエルがライオンの洞窟に投げ込まれるが無事に帰還するという筋の話とともに伝えられているアポクリファである。テキストにお いて「預言者ダニールがバビロンで殺した蛇」とあるのは、これらアポクリファを踏まえている。テキストの「ヴィール」はベル神のことである。ところが、ダ ニエル記外典に当たれば一目瞭然であるが、ダニエルは確かにヴィール(ベル神)と蛇の両方を退治しているものの、両者は各々別物である。即ちヴィール(ベ ル神)は蛇ではない。この経緯は2)写本のみが正確に伝えている *3 。
アポクリファにおいてダニエルが倒したベル神と蛇が、テキストの作者によって内容的に混同されて同一視され、その上さらに、名称の音声上の類似か ら南スラヴ固有の妖精ヴィーラとも同一視されることになったと考えられる。
次に、イスラムについての言及であるが、現代の我々から見るとそれらはやはり珍奇なものと映る。
まず第一に、モハメッドはイスラムの司祭жрецと呼ばれているが、周知のように、イスラム教においてモハメッドは言うまでもなく最大にして最後 の預言者である。イスラム教を奉じる人々が、マホメットが異教司祭を指す*рецという言葉で呼ばれているのを聞けば、冒涜だと捉えることは間違いがな い。このテキストでは、故意の貶しめがなされているのである。
さらに、『講話』の中でイスラムの名前が出てくる箇所がもう一つある。エジプト神話のオシリスに関する言及
ヴィールに関する記述、モハメッドやイスラムの奇習(と、このテキストの作者が考えている)についての記述は、少なくとも、4世紀の聖者が知るは
ずもないことであり、現にこの原典に当たると考えられている『聖グレゴリオス講話第39話 神の光のなかへ』
ナイル河に関する言及は、原典と原典を非常に正確に反映した南スラヴ語訳では「ナイル河が実りをもたらしてくれるからと言って、穀物の実りをもた らすものとナイルを賛美してナイルを貶しめてはいけない」となっており、その文言には古代民衆のナイル崇拝の根深さに対する聖グレゴリオスの慎重な配慮が 感じられる。これに対して、本『講話』では「エジプト人たちは『実りをもたらすナイルよ、穀物の育ての主』と唱えて、ナイル河に捧げ物をする」と、エジプ ト人たちと捧げ物をする風習に対する非難へと、論難の主旨が変わっている。本『講話』のなかで繰り返し論難の対象となっているのは、偶像に対する捧げ物で あるから、上記のナイルに関する言及は、北東ルーシのキリスト教聖職者の問題意識によってテキストが変容を被った一つの例と言える。
同様の例のなかでさらに面白いものとして次のようなものを挙げることが出来る。
本『講話』テキストの中に「モコシとマラキアを崇拝している」という箇所がある。スラヴ人の神格モコシと並べられている以上、マラキアも同様に神 格と捉えられたと判断できるが、この部分はギリシア語原典では「優雅さを重んじている」ほどの意味である。これは写字生らの奔放な解釈によって本来のテキ ストが内容的な改変を被っているわけである。ここでは、優雅さという抽象概念が神格におき変ってしまっている。
さらに、この部分はギリシア語原典と南スラヴ語訳では次のように書かれている。“сижебо и малакию чтоша и буесть почтоша”“Οι γαa`ρ αυ’τοιa` καιa` μαλακιa'αν εa'τιa'μησαν καιa` θρασυa'τηтα ε’σεβαa'σθησαν”「堕弱を重んじ、向こう見ずたることを尊んでいる。」これが、我々のテキストでは次のようにな る。“И Мокошь чтуть,и Малакию,Килу вельмипочитают,рекущи‘Еуякыни’”「モコシとマラキ アを崇め、『ブヤキニ』と言ってキラを大変深く崇敬している。」問題は“Еуякыни”なる語の解釈であり、『11-14世紀古代ロシア語辞典 (Словарь дренерусского языка(=ⅩⅠ-Ⅹ Ⅳ)』に至っては不明として語義の深求を放棄している。“Еуякыни”なる 言葉がこの文献にしか見いだされない以上、古代ロシア語のコンテキストから見てこの判断は確かに妥当なことと言える。
しかし、原典並びに南スラヴ語訳に当れば、この語がθρασυa'τηs=буесть「向こう見ずであること」に対応することがわかったはずで ある。古代ロシア語では通常буявый、буякьがそれに当たる。我々のテキストの作者は恐らく南スラヴ語訳テキストの解釈に苦しみ、前出のマラキア を神格と解釈したことに引き擦られて、「向こう見ずであること」を尊崇の対象とは考えず、別の神格キラ(写本1)を除くすべての写本にこの語が存在する が、この語が何に由来するのかは全くの謎である)が崇拝される理由と解釈したのであろう。
因みに、以上の比較から、テキストの伝承史における断絶は南スラヴ語による翻訳と中世ロシアの諸ヴァリエーションの間に生じていることが明らかで ある。北東ルーシにおいてテキストは、写字生たちの奔放な自己解釈により変貌を遂げたのである。
こうした自己解釈によるテキストの変容が最も著しいケースとして、「アルテミドとアルテミジア」という神格が挙げられる。アルテミジアがアルテミ スを示すことは明らかであろうが、アルテミドなる神格はそもそも存在しない。このことを私達はどう考えたらよいのだろうか。
北東ルーシ民衆は「ロードとロジャニッツァ」を信仰していた。この「ロードとロジャニッツァ」信仰を『講話』の作者が異教神話の典型であるギリシ ア神話の概念で理解しようとした結果、おそらくはギリシアの神々についての知識を中世の写字生が十分に持っていなかったため、アルテミドなる神格が案出さ れたのであろう。
アルテミスは多産・出産の守り手としても崇拝されていたから、北東ルーシではこれと同じ役割を果たしていたロジャニッツァと同一視され、ロジャ ニッツァは対応する男性の神格ロードと常にペアを作っていたため、アルテミジア(アルテミス)があるならばロード神にあたるアルテミドもあるはずだと作者 が考え、実際には存在すべくもない神格がしるされたのであろう。
以上に、ギリシア語原典とルーシにおいて成立したテキストとの主なる相違点を述べてきたわけであるが、翻って次のように問いかけたい。ギリシア語 原典と後世の改作を結ぶものは全くないのであろうか。写字生たちが聖グレゴリオスを拠り所とした理由を、キリスト教典礼確立に力を傾注した大聖者という権 威以外に求めることは出来ないのだろうか。
ギリシア語原典の中で記述されているのは、アフロディテ、セメラ、デュオニュソス *8 、オシリス、などギリシア神話やエジプト神話の神々への崇拝に対する論難、エレウ シスの秘儀、スパルタの血生臭い風習、ファロス崇拝、カルディアの占星術などに対する論難であり、聖グレゴリオスが非難の対象としているのは、一見して、 汎神論的な風土とそれによってもたらされる奇習、多くの場合、血生臭い奇習だったことがわかる。聖グレゴリオスの激しい論難の精神から、私達は一神教を護 り通し、それらの血生臭い風習から人々を解放しようと志す強固な護教への意思を読み取ることが出来るだろう。
文献学的な正確さの欠如、神話学的な知識の不足のため生じた事実の歪曲など、このテキストが備える大きな欠陥にもかかわらず、写字生が聖グレゴリ オスから受け継いだ最も重要なものはこのキリスト教の護教精神にほかならない。一神教としてのキリスト教の性格を守るということへの堅い意思である。文献 としての正確さが損なわれているとしても、汎神論的な風土への挑戦という精神は脈々と受け継がれ、その結実の副産物として、中世ロシア農民の習俗の詳細が 克明に書き記された。このテキストにおいては、14・15世紀ロシアの農民習俗に対する細やかな観察に基づく一連の記述が原テキストに挿入されているが、 まさにこの挿入箇所のゆえに『聖グレゴリオス講話』は、ガリコフスキー、アーニチコフ、ゼレーニン、ブリュクネル、オルロフ、コマロヴィッチらの文献学 者、民俗学者、神話学者らの関心の対象となってきたのである。
このことは多分に逆説的である。聖グレゴリオスから受け継がれた護教精神こそが本テキストにおける最も大きなテキストの変容を引き起こしたのであ り、翻訳文献としての質の低下を補って余りある独自の価値を生みだした。原典の翻訳に当たる箇所が往々にして難解で意味が判らなくなるのに対して、こうし た挿入箇所は書かれている内容も明晰であり、その記述もおおむね正確で、中世ロシア民衆の生活の断片を伺い知ることの出来る貴重な資料となっている。
ここでは、ペルーン、モコシ、ストリーボグ、ダージボグなど原書年代記など文献で知られている神格、ウプイリやベレギニャのように近代まで生き 残った妖怪妖精、スヴァロジッチ、ヴェレアル、クトン、ベリャ、オビルハ、ペレプルトなど時代とともに忘れ去られた神話的存在が言及されている。その一方 で、中世ロシア民衆の宗教生活の根幹をなしていた自然崇拝と祖先崇拝をめぐる様々な儀礼が列挙され、あたかも中世ロシア民衆の異教儀礼の百科事典のような 様相をさえ呈している。宗教儀礼に端緒を持つと考えられる子供の遊びさえ作者の視野に入っている。中世ロシア民衆の風習に触れたこの箇所は、19世紀以降 に始まった民俗学資料の蓄積を逍猟しながら、新たに論じられるテーマであると思われるので、本稿ではこれ以上触れない。
ただ、中世期には文字は教会の専有物だったことについて注意を喚起したい。ロシア中世の教会文献の中では、というより、おしなべて書き言葉そのも のの中で、農民の生活習俗そのものに注意が払われることは全くなかった。唯一の例外が『グレゴリオス講話』のように、異教と認定され、論難の対象となった 場合であり、その結果、繰り返して言うが、本テキストの記述は中世ロシア農民の宗教や生活習俗を知る上で重要な資料となったのである。
本テキストの先行研究について触れておきたい。
まず、スレズネフスキーが『文書史料に基づく古代ロシア語辞典のための資料』
しかし、これらの先行研究を集成して『グレゴリオス講話』ロシア・ヴァリアントのテキストを確定し、さらに、チュードフ・コレクション写本による
プスコフ・ヴァリアントの紹介をも含む本格的な仕事を行なったのはガリコフスキーである。かれは1913年出版された著書『キリスト教会の異教残滓との戦
い 第二部』
この著書には、本テキストの他にも、ロシア正教会が民衆の異教的な風習に対して何世紀もかけて行なってきた文書による言論活動の成果が集められて いる。『聖グレゴリオス講話』には20ページ近くが割かれ、テキスト学的な検討とテキストの生成をめぐる若干の考察が行なわれている。1913年版のこの 資料の集積をもとに、ガリコフスキーは1916年ハリコフでその理論篇とも言うべき『キリスト教会の異教残滓との戦い 第一部』を上梓した。
さらに1914年全く同じタイプの、そして、ガリコフスキーの業績に劣らず重要な仕事が当時の首都ペテルブルグで出版された。アーニチコフ『異教
と古代ロシア』
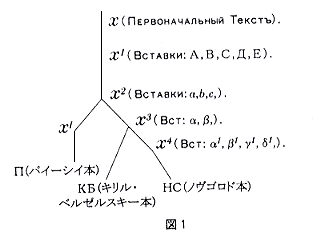
アーニチコフは、1)・2)・3)写本間の語句の異同を明らかにしているばかりではなく、その成立に影響を与えたテキスト(『キリストを愛する某 者の講話』、『聖金口イオアネス講話』、本『講話』の南スラヴ語ヴァリアント)の存在を指摘し、綿密な考察の対象としたことを始めとして、ほかにも多くの 有益な示唆を与えている。アーニチコフによる研究の価値は、全体として捉えると、『聖グレゴリオス講話』のテキスト生成というテーマに先鞭をつけたものと して極めて高い評価を与えることが出来る。しかしながら、このアーニチコフの優れた研究をもってしても、『聖グレゴリオス講話』テキスト伝承の歴史が決定 的に明らかになったわけでは、決してないのである。
まず第一に、アーニチコフは写本間の直線的な影響関係を提示しているが、この想定は適切ではないように思われる。なぜなら、写本間の影響関係の系 統樹をつくるためには、5点という写本の点数は決して多い数ではない。語句の異同のみからこれら五点の写本間の関係を直線で結んでしまったならば、伝承さ れなかった写本が存在する可能性を除外してかかることになる。
さらに、アーニチコフは写本3)キリル・ベルゼルスキー写本No. 43/1120(16世紀)テキストと1)パイーシイ文集(14世紀)テキス トとの間に明らかに見て取れる近親性を過小評価し、むしろこれらのテキストの語句の瑣末な差異にこだわって、3)写本(16世紀)テキストが写本2)ノヴ ゴロド・ソフィア・コレクションNo. 1285(15世紀)テキストの影響の元に成立したと主張しているが、この点はかれの考察の中で最も再考を要する 点である。
1)写本と3)写本が成立年代に200年以上の開きが予想される事実と折り合いをつけようとして、アーニチコフは3)写本の成立を2)写本と関連 づけて考えることになったのだと思われるが、実際にテキストに当たって再読すれば(アーニチコフの研究では語句の異同のみでテキスト自体は与えられていな い)、1)写本と3)写本の近親性は明らかであり、3)写本の成立に与えた2)写本の役割を1)写本のそれより大きく評価することは到底出来ないはずなの である。瑣末な語句の異同にこだわり、アーニチコフは木を見て森を見ずの錯誤を犯しているとは言わなくてはなるまい。この点に関しては具体例に当たって後 で詳述したいと考えているが、アーニチコフは全般的に直感に頼って結論を急ぎ過ぎる嫌いがある。
ガリコフスキーとアーニチコフの仕事は今日の研究の基礎をつくった点で極めて重要な仕事であり、両研究書の役割は全く古びていない。しかしなが ら、同時にこれらの先行研究を注意深く検討してみると、以上挙げたようにいくつかの点で難があることも否定できないのである。それらを整理すると次のよう になる。
まず、この二つの仕事はほとんど同じ時期に独立して行なわれたものであり、刊行まで両者は互いの研究において知るところがなかったために、成果の 突き合わせができなかった。そして、この二人の優れた研究者の成果の突き合わせは今に至るまで行なわれていない。もしも両者の成果の突き合わせができてい たら、各々の発見相互に横たわる有機的な連関が見いだされ、『聖グレゴリオス講話』ロシア諸ヴァリアントのテキスト構成の歴史に新たな光が投げ掛けられて いたことは確かである。
さらに、ギリシア語原典、南スラヴ・ヴァリアント、南スラヴ起源の注釈本の存在について触れながら、両研究書ともテキスト学的な考察にそれらが十 分に活かされていないこと、アーニチコフの著作についてはテキスト学的考察が部分的な考察からテキスト伝承の歴史全体を類推する荒っぽさがあること、ガリ コフスキーに関しては写本の略号等に関する知識が当時まだ整備されていなかったため誤記等が多いこと、また、ガリコフスキーは資料集の作成に当たってすべ ての資料を写本に当たって確認しているわけではないことなどが、そのほかの問題点として挙げられよう。
こうした研究史上の問題を考慮にいれると、今世紀中葉新たに発見されたテキストをも視野にいれて『聖グレゴリオス講話』テキスト伝承の歴史を今一 度検討することは、研究上重要な意義を持つと考えられる。以上の理由から、新しく発掘されたテキスト、すなわち、プスコフ・ヴァリアントのテキスト確定と 『聖グレゴリオス講話』諸ヴァリアントの生成過程に関する新たなる考察が望まれているところであった。本研究はこうした学問的な要請に基づいた試みである ことを付記しておく。