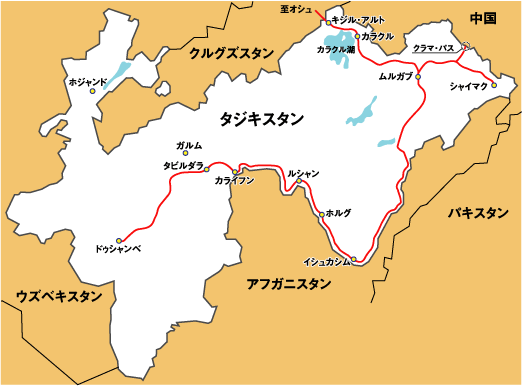
パミールの旅 |
私にとって、中ロ国境4000キロの画定問題が、中央アジア・中国国境3200キロの画定問題と、旧中ソ国境交渉の経緯からリンクしていたことは僥倖であった。とくにタジキスタンのパミール高原(ゴルノ・バダフシャン州)の領土問題を、アムールとウスリーの合流点にある黒瞎子(ヘイシャーズ)島の問題とセットで解決する交渉がゴルバチョフ時代に進んでいたらしいこと、また独立したばかりのカザフスタン、クルグズスタン、タジキスタン(この3国はそれぞれおよそ1700キロ、1000キロ、400キロの対中国国境をもつ)が当初、中国との領土問題に関する交渉を拒否し、ロシアの仲介で「4(ロシア+中央アジア3国)+1(中国)」の枠組(「上海ファイヴ」の原型)において交渉継続に同意したことなど、興味をそそられた(※1)。こちらの領土問題もある程度フォローしなければ、私の東部国境の仕事も説得力が欠けよう。折から、上海協力機構(2001年6月結成)への関心が学界で高まっていく。半可通の学者たちは、これをもって中国とロシアが中央アジアを巻き込んで「反米同盟」をつくろうとしているなどと言い始めた。私は上海協力機構のルーツが国境交渉にあることをアピールし、半可通のプレイ・アップと闘うべくカンパニアを展開した(※2)。
中央アジアに行きたいと強く思った。意外に思われるかもしれないが、私が初めてかの地を訪れたのは、2002年2月、スラブ研究センターに赴任してすぐのことだ。このときはカザフスタンとクルグズスタンを中心にせめた。アルマトゥからドルージバ・阿拉山口を鉄路で越え、ウルムチにいき、イニンからホルゴスを自動車道で越え、ビシュケクに入った。二回目は2003年2月、タシケントとドゥシャンベに飛んだ。両国の「仲の良さ」を反映してか、首都間には直行便がないため、陸路でホジャンドに入り(タジキスタン側の国境コントロールはカラシニコフを担いだタジク人兵士が数十名もいて、さすがの私も写真を撮ることができなかった)、そこから飛行機で数千メートル山々を眼下にドゥシャンベに向かった(冬期、陸路は閉鎖)。12月、ついに憧れのトルクメニスタンを訪れたことで、私の願いは全てかなった(※3)。
日ロ関係においては、領土問題があるから、ロシアの在外公館にあまり借りをつくりたくない。そう思い続けてきた私は一度の例外を除いて、自分から足を運んだことはない(人に連れていかれたことは、あと二度ほどある)。しかし、中央アジア諸国と日本の間に難しい懸案事項は存在していないため、在外公館に力添えをお願いするのにためらいはない。国際問題研究所との連携により、上記の中央アジア諸国で面談のアポをとる際には、多くを在外公館のお世話になった(ただし、トルクメニスタンは例外で、すべて現地飛び込み取材に徹した。兼轄するモスクワ大使館を通じて事前に面談の手配するとビザ取得に差し障りがある可能性を示唆されたからである)。
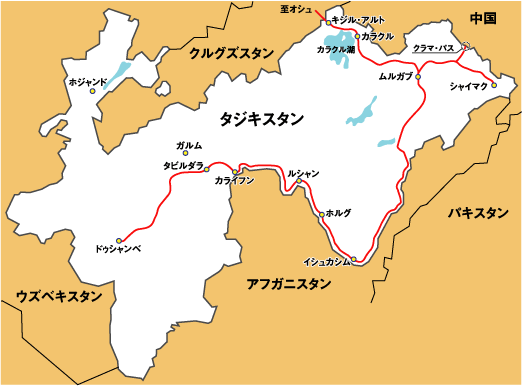
-Ⅱ-
タジキスタンの日本大使館からは格別な待遇を得た。二年前から一人で大使館の立ち上げに取り組んできた鎌田祟志一等書記官は、国問研を通じた私の要望に積極的に応えてくれた。折から大使館には、ペルシャ語専門家の三好功一臨時大使が赴任されたばかりであり、館員一同の熱意が伝わってきた。私の当初の狙いは、「解決など到底無理」と長年、いわれ続けてきた中国とタジキスタンの国境問題(2002年5月に電撃的に画定終了を宣言。中国側もタジク側も詳細については情報を統制。北京の専門家でさえ、その報に驚き、詳細を知らされてはいない)の内実を知ることにあった。だが、ドゥシャンベでの面談の成果はかんばしくなかった。政府関係者の口は重く、親ロシア的なとあるタジク研究者は中国大使館筋の情報として(公称の1000平方キロ弱ではなく)4000平方キロが中国に移管されるとさえいった。結局、移管される場所も確定できず、不確かな伝聞情報をとるのが関の山であった(※4)。もう一度、来なければならない。そう思った私は、実際にパミール高原の対中国国境を訪問できないかどうか思案を重ねた。
2003年夏、私の申し出を大使館は再び歓迎してくれた。これはありがたかった。ゴルノ・バダフシャンにはタジク政府の許可なしで入ることはできない。だが許可をとるためには現地大使館のレターが必要である。それゆえ、パミールは一般のツーリストやバック・パッカーが立ち入れない垂涎の地とされている。アムールなどと違って、ここでは大使館の支援なしに調査することなど、そもそもが不可能なのだ。大使館側の窓口となった藤井啓之二等書記官とメールのやりとりを続けた。ロジの支援のみならず、同行サポートを約束してくれた彼は、高度4000メートルの山地をほぼ8日間かけて踏破するスケジュールを組む。訪問先は、アフガニスタン国境のピャンジ河、中国国境に近いシャイマク、そしてクルグズスタンとの国境点キジル・アルト。ゴルノ・バダフシャンの州都ホログ出身の専門家も同行し、ランドクルーザー2台を連ねての旅となった。宿には、その宗教的理由からゴルノ・バダフシャン州の各地で熱心に支援を続ける、アガハン基金(※5)の宿泊所が予定された。10月5日(初日)の夕方、ドゥシャンベから300キロ近いゴルノ・バダフシャンの玄関口カライフン(人口3000人)に到着した私たちは宿泊所に温水シャワーも電気もきていることに意外な感じをもった(この直感は正しかったことが後で判明する)。1週間は着の身着のまま、風呂にも入らない覚悟で、水もペットボトル2リットルを4ダースほどドゥシャンベで仕入れてきたからだ。
 |
|
| [写真1]河の向こうからこちらを見つめるアフガン人 |
|---|
タジキスタン側は、アフガニスタン側に比べると道の路肩も広く、(内戦のおかげで電気はきていないと思われるが)シベリアあたりでみられる木の電柱が川沿いに敷設されている。ただ道はよくない。アップダウンばかりが、ところどころが山からの水で河原と化しており、ランドクルーザーでも徐行運転を強いられる。くだんの専門家はソビエト時代にはアスファルトで整備されていたのだが、内戦の結果こうなったと説明する。ソビエト時代、対面のアフガン人からみたタジク人の生活は「文明」そのものであった。だが今では、河を隔てた両国民の暮らしぶりは接近してしまった。一度「文明」を味わったタジク人に比べ、はなからそれを知らないアフガン人がはるかに強靱だと、彼は続けた。見晴らしのよいところで車を降りる。トイレをすまそうと河沿いに近づくと、大声で止め
られた。見晴らしのよいところは、ムジャヒディンにそなえて敷設された地雷がいまでも回収されずに残されている(写真2:峡谷 3:戦車)。
 |
 |
|
| [写真3]地雷と戦車:むこうの小道は河を挟んだアフガニスタン | ||
| [写真2]河むこうはムジャヒディンの攻撃路、手前はタジキスタン |
 |
| [写真4]ウォッカ献呈後 |
たいてい、この種の「戦略」的な場所には国境警備隊の基地がある。検問を受けるが、許可証をもち、大使館の車にのっている私たちは基本的にフリーパスだ。ここに本当にロシア人がいるのだろうか。私は検問所で警備隊のボスに表敬をしたいと申し出た。だが、なかなか彼らは出てこない。うかつには対応できないのだろう。私はシベリア極東で学んだ手法を使った。日本の教授からのプレゼントを手渡したいと伝えてもらうのだ。すると隊長はすぐに現れた。紛れもなくロシア人だ。ドゥシャンベで買い込んできたウオッカ1本を新聞紙にくるんで渡す。喜んで記念撮影に応じてくれた(写真4)。
-Ⅲ-
調子にのっていると、たいていひどい目にあう。強行軍をするということは、それだけ多くの現地を通過するということだ。ルシャンで昼飯をごちそうになる。ウオッカで乾杯。夜はホルグだ。ゴルノ・バダフシャンを統括する国境警備隊のボスがでてきた。さらに乾杯。これで終わりだと思って、「中国式宴会対処術」(※6)を駆使してがんばったのが、裏目にでた。夜中についたイシュカシムでまさかの接待をもう一度うけ、3連チャンの乾杯。すでに標高2000メートル以上に達していたが、私は平地の感覚のままに飲んだ。平地でも飲み過ぎである。さらに高度が上がる翌日、私は地獄のなかにいた。
7日の朝起きて、一踏ん張りした後、私は車の後部座席で横になったまま、ほとんど動けなかった。途中、なんども車をとめて用を足しにいく。すでに標高は3000メートルを越えている。同行者はゆっくり歩けと忠告するが、聞く余裕もない。高地での急激な動きがますます私の体調の「良さ」に拍車をかけた。恐るべき悪路であったような気もするが、私の記憶は欠落している(当然、私の日記も空白のままだ)。
いよいよゴルノ・バダフシャン最東部、標高4000メートル近いパミールの中心ムルガブに到着したが、私はこの夜、ろくに食事もとれずにベッドに入った。以後、私は道中、いっさいアルコールを口にできなかった(私の人生で1週間も酒をのまないとは何十年ぶりのことだろう)。かわりに藤井書記官が、大車輪の活躍で接待の相手をしてくれた。翌日、ムルガブの市場を散歩した。中国の米が入っていた。ウオッカは「バトケン」という名前のオシュ産クルグズ製であった。そう、ここの住人は9割以上がクルグズ人なのだ。にもかかわらず、ここはタジキスタン領である。流通はアクセスの良い(道路も整備された)オシュに多くを依存している。国際政治においては、隣の「大国」ウズベキスタンに対して、同じ「小国」として連帯している感もあるタジキスタンとクルグズスタンだが、きっと両国間にもいろいろな難問が横たわっているに違いない。
8日からが旅のハイライトである。4600メートルの山を越え、高度4000メートル、ムルガブから140キロの地点にあるカラクルの国境警備隊基地を訪問する。ここで昼飯をごちそうになったが、彼らは基地の全てをみせてくれた。2002年末、ロシア軍は(対アフガニスタン国境と異なり)対中国国境の警備をタジク軍に全面移管したが、立ち去る際に、電気・通信設備を破壊し、ディーゼル燃料や車両をほとんど持ち去った。警備隊の隊長は、ロシアのひどさを訴え、「この冬も越せない」と同行の大使館員に日本からの援助を懇願していた(※7)。私は彼らの懇願をそしらぬ顔で、国境警備隊の詰所につきものの警備塔に登った。中ロ国境の旅でいやというほど目にしてきた(そして時々、痛い目にもあった)塔に登る機会を得た私は興奮気味であったが、同行のタジク人に「ゆっくりのぼれ」といわれて、ここが河の国境ではないことを思い出した。
カラクル湖を横目にみて、30キロ先のクルグズスタンとの国境、キジル・アルト(※8)に向かう。ここは10月初旬というのに、すでに雪に覆われていた。風が吹きすさび寒い。警備隊長(タジク人)にウオッカを差し入れしたが、ここの冬は基地よりもさらに厳しいだろう。
 |
| [写 真5]三国国境に近いシャイマク |
-Ⅳ-
その夜、ホルグに戻る。ここでも2000メートルは軽くあるはずだが、私たちにとってはもはや平地の感覚だ。久しぶりの「文明」の光がまばゆい。4日ぶりのシャワーを浴びた。一晩中、灯りがともっているため、夜中にもトイレにいける。水洗だ。ホルグにはドゥシャンベと結ばれた飛行場もある(アフガニスタン国境の河川をすれすれに離着陸する)。高級ホテルでは、常時接続のインターネットは無理だが、メールの送受信もできるそうだ。だが、ここが広大なゴルノ・バダフシャンのわずかなオアシスであることを忘れてはならないだろう。
10日夜、カライフンに到着。行きと同じ宿泊所だ。変わらぬ風景に見えるが、出迎えた宿の責任者がおまえたちは幸運だという。私たちが出発した直後から、今、到着する直前まで、水も電気も止まっていたらしい。断水は続いていたが、電気は数時間前に復旧したという。私たちは旅の成功を祝って、乾杯をした。私の代わりに藤井書記官は大いに飲み、宿の主人に「もう飲めない」といわしめた。そのとき、運転手の2人がようやく帰ってきた。今回の旅では、毎日必ず1本はタイヤが破損していた(日によっては、2本破損したこともある)。その日のうちに、タイヤの修理をしなければ次の日の旅は不可能だから、彼らは街にたどりつくやいなや、夕食の前に、修理屋を探して奔走していたのだ。ゴルノ・バダフシャンの山の旅は、多くの人々の支援なしには、旅そのものが成り立 たない。2人の運転手には心より敬意を表したい。
ところで道中、私たちの車はかのガルム近辺(実はガルムでなくて、ガルムを通ってクルグズスタンに向かう分かれ道を、逆にゴルノ・バダフシャン方向へとり6キロほどタビルダラへ向かったところ)を通過する。1998年7月に秋野豊さんが射殺された現場だ。2月のドゥシャンベ訪問の際、大使館の方々は、秋野さんの職務室(旧UNMOT)と玄関にはめられた慰霊版、さらには住んでいた部屋にまで、私を案内した。そして、今回もまた秋野さんを知る現地の責任者との面談を組んでいてくれた。彼らの先導で車を走らせる。気持ちよい峡谷の旅の途上、一瞬、見通しが悪く、妖気ただよう空間が現れる。そこが現場である。現場横の峡谷を望む小高い場所には、記念碑が置かれている(写真6)。現地の誰もが一様に、秋野さんの名前を出して感謝を表明していた。「私たちは一番つらい時期に助けてくれた人の名を忘れることはない」。ドゥシャンベでは忘れ始められている彼の名も、ここでは確かに人々の心に刻まれている。
 |
| [写真6]一番左に「秋野豊」の名前が刻まれている |
2003年7月、スラブ研究センター夏のシンポジウムの際、私たちはレセプションの開会前に、ささやかながら秋野さんの追悼5周年に関する催しを行った。イラク戦争を契機として、日本の「国際貢献」の意義を遠くから声高に叫ぶ人たちが増えているが、秋野さんが現地とかかわろうとした姿勢の原点を私たちは忘れてはならないだろう。