中国における旧ソ連研究
Copyright (C) 2000 by Slavic Research Center,Hokkaido University.
All rights reserved.
はじめに−ポスト冷戦下の胎動
1991年末にソ連が崩壊して以来、すでに9年が経過した。世界中に衝撃をもたらしたソ連崩壊のニュースであったが、事態をもっとも深刻に受け止めていた国の一つが同じ社会主義体制をとり、図們江のロシア及び朝鮮との三国河川国境点から始まる東部約4000キロ、あいだにモンゴルを挟み、タジキスタン及びアフガニスタンとの三国山岳国境点で終わる西部約3000キロを越えて対峙してきた中華人民共和国であった。
1991年の「八月クーデター」に直面した中国指導部が当初、クーデター政権を歓迎したこと、92年初頭、ソ連崩壊の余波で強まりつつあった保守的な潮流を が「南方講話」でうち破り、「改革・開放」を後戻りできないところまですすめたこと、そして、中国が一挙に経済発展の波にのり、いまやロシアをしのぐ実力と自信をつけつつあること、これらは周知の事実である。
が「南方講話」でうち破り、「改革・開放」を後戻りできないところまですすめたこと、そして、中国が一挙に経済発展の波にのり、いまやロシアをしのぐ実力と自信をつけつつあること、これらは周知の事実である。
歴史的にも地政学的にも、また政治・経済的にも、「隣の大国」ソ連(ロシア)は中国にとってもっとも重要な研究対象の一つであった。中国語を解するロシア人専門家に比べれば、ロシア語が自由な中国人専門家の数ははるかに多い。中国において欧米や日本に遜色のない規模で組織的にロシア研究が行われてきたことに疑いはない。例えば、国境地域の黒龍江省社会科学院シベリア研究所や黒龍江大学ロシア研究所はロシア極東の代表紙のみならず、市や国境点レベルでの新聞や雑誌なども収集しており、その翻訳や分析は内部で回覧され、中国の「学界」がロシア研究を行う際の基本的な資料となっている。
にもかかわらず、中国の研究者たちの業績が広く世界に評価されることはまれであった。ひとつには文化大革命の影響も大きい。1966年以降のほぼ10年間、大学の機能は低下し、多くの学生や若手研究者が下放された。文化大革命が終り80年代に入ると、中国の研究者たちは教育や研究の再興を誓い研究所内部や学会の会議において、かなりの程度、自由に論議を行うとともに地に足のついた研究を再開した。だが、社会主義体制による制約は外部での自由な見解の公表や論議を妨げてきた。社会主義体制は「学界」に対して、「政府への政策の提言」と「政府の政策の宣伝」を強く求め、公開雑誌への掲載には党指導部による「校閲」が不可欠であり、国際会議で政府の公式見解から離れた論議をすることも容易でない。それはある意味でペレストロイカ以前のソ連の「学界」と似ている
(1)
。現在でもこの大きな枠組自体が崩れたわけではない。
だが1992年以降の「改革・開放」の加速化は中国の「学界」に対しても新たな転換を要求している。中国社会科学院東欧中亜研究所はソ連東欧研究所から名前を変えると、その紀要『東欧中亜研究』を93年に早くも公開雑誌とした。この雑誌は現在、『 選集』や『人民日報』ばかりを注記した旧来のスタイルから脱却し、掲載論文には外国の研究やロシアの新聞・雑誌などから直接的に引用を行うケースが多くなっている。96年からは地方紙に課せられていた制約もはずされ、外国人も『綏芬河日報』、『満州里報』など国境点でロシアとの日常の接触を報じる地元紙を読むことができるようになった(もっとも、場所によっては地元の官僚的対応から入手できないケースも少なくない)。長年、一般公開が待望されていたシベリア研究所の紀要『シベリア研究』も遅蒔きながら、99年1月号から公開雑誌となった。
選集』や『人民日報』ばかりを注記した旧来のスタイルから脱却し、掲載論文には外国の研究やロシアの新聞・雑誌などから直接的に引用を行うケースが多くなっている。96年からは地方紙に課せられていた制約もはずされ、外国人も『綏芬河日報』、『満州里報』など国境点でロシアとの日常の接触を報じる地元紙を読むことができるようになった(もっとも、場所によっては地元の官僚的対応から入手できないケースも少なくない)。長年、一般公開が待望されていたシベリア研究所の紀要『シベリア研究』も遅蒔きながら、99年1月号から公開雑誌となった。
中国の研究者たちは自国の経済発展に歩調をあわせるかのように自信にあふれ、以前とは比較にならないほど自由にそして率直にものを語りだしたように思う。本稿の狙いは変貌をとげつつある中国の「学界」における旧ソ連研究の息吹と胎動を紹介することにある。本稿では1996年に黒龍江教育出版社から「当代国際関係と戦略研究叢書」と銘打って出版されたシリーズのなかから、劉徳喜・孫岩・劉宋遠『ソ連崩壊後の中露関係』(
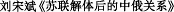 )、及び広程『中国と中央アジア新国家の関係』(
)、及び広程『中国と中央アジア新国家の関係』(
 )を取り上げたい。
)を取り上げたい。
この二冊を取り上げるのは、それがポスト冷戦時代の中露関係および中国・中央アジア関係を初めて体系的に扱い、かつ一般向けに公刊されたものであるからだが、以下の二つの理由によってさらに補強される。第一に、この二冊が1950年代以降に生まれ今や第一線にたちつつある執筆陣によって書かれた点である。中国の新しい世代の研究水準をはかるには適当な素材といえよう。第二に、本書を検討することで中国の学界が旧ソ連問題に関して、どの程度まで一般公開のかたちで議論しうるようになったのか、そしていまだにタブーとされるものは何かを明らかにすることができると思われるからである。本稿では便宜上、二冊の本を別個に書評するかたちで論をすすめるが、本稿の分析が上記の問題意識を前提としてなされたものであることをあらかじめお断わりしておきたい。
1. 中露関係を理解する「糸口」
−劉徳喜・孫岩・劉宋遠『ソ連崩壊後の中露関係』
ポスト冷戦下の国際関係において、中国とロシアの関係はそのユニークな性格によって多くの政治家や学者たちの注目を引いている。中露は現在、双方とも経済体制の転換を迫られ、政治的先行きの不透明さを抱えているが、日米安保条約の強化(「新ガイドライン」)及びNATOの攻勢(東方拡大・ユーゴ空爆)に対抗するため、また国内の経済発展を加速化させ政局を安定化させるため、歴史上のこれまでのいざこざをとりあえず棚上げし、1990年代の流行り言葉にすらなった感のある「21世紀に向けた戦略的パ−トナーシップ」を宣言した。
本書『ソ連崩壊後の中露関係』は中露関係における歴史的な深淵、つまり、ロシア革命の衝撃から、中国革命とソ連の関係、中ソの同盟と対立、ペレストロイカと中ソ正常化などを概観した後、中国と新生ロシアとの関係再構築・外交関係の樹立、「戦略的パートナーシップ」を宣言するまでのプロセスを描くと同時に、中露双方の関係緊密化を促した国内・国際上の諸要因を分析し、中露関係に現存する問題点及びその関係発展を損ないかねない幾つかの困難を指摘している。
著者によれば、中国の北の隣国、ロシア(ソ連)が友人であった歴史は、敵としての歴史よりはるかに短い。この意味で、ソ連崩壊が中国に一種の安堵を与えたことは確かである。その「膨張戦略」により、中国の安全保障に最も脅威となってきた「超大国」ソ連の衰退は中国の国益にみあうものといえる。現在、中国はソ連の継承者たるロシアが国力はさほど強くはない安定した国になることを期待しており、その体制転換が成功して資本主義大国になることを決して望んではいない。万一、ロシアの「体制転換」が成功すれば、それは西側の民主制、私有制及び市場経済モデルの効果を実証するだけでなく、強大なロシアが再び中国のライバルとして勃興する可能性が大きいからである。
だが他方で、「プロレタリア独裁」、「マルクス・レーニン主義」などのイデオロギーを共有し、おなじ社会主義体制をもつソ連の滅亡は決して望ましいものではなかった。この点を著者は「国家間関係の変遷」という章で率直に述べている。「東欧の激変・ソ連の解体により世界の社会主義事業と共産主義運動は巨大な打撃と重大な挫折を受けた。……これらの事態は、共産党が権力をもち社会主義の道を歩む中国にとって、大変不利な局面であり、厳しい情勢であった」(65頁)。
苦悩は、中国側がソ連崩壊の直前、ロシア連邦がもはやソ連政治の中で決定的な勢力となった時点においても、ソ連の存続を支持するためソ連政府との関係を重視し、当時のエリツィン訪中の希望を拒否した点に集約されている。これが中露関係の初期の展開にマイナスの影響をもたらしたことは言うまでもない(67-69頁)。しかし、「情勢を真剣に検討した結果、中国政府はすぐに政策を変え、ロシアとの外交関係を樹立し、平和共存五原則に則って善隣友好関係を展開することを決定した。これにより中ソ関係が中露関係へと順調に転換した」(69頁)。
1991年から92年にかけての対ソ連・ロシア問題についての中国の政策決定過程は、それ自体興味深いテーマである。これまでの先行研究は「西側中心外交」をとるロシアによる「中国軽視」の側面に分析の力点を置くことが多く(2)、中露関係が改善された契機が今一つ不明瞭であった。この意味で、中露関係の改善がロシア側にではなく中国側の路線転換に多くを依存しているとする本書の示唆は、有意義といえる。次に読者が期待するのは「情勢を真剣に検討した」際の具体的な争点とそれをめぐる議論の分析であろう。
さてソ連崩壊直後の苦悩から立ち直った中国外交であるが、その後の中露関係の展開を著者は、次のように整理する。1)中国による現実の変化の承認、2)ロシアの「西側中心外交」の失敗、3)中露関係の初期発展及び「建設的パートナーシップ」の確立、4)中露関係の「戦略的パートナーシップ」への展開。著者は「ロシアと関係発展を図ろうとする中国の主動的な対応を背景として、地政学的な配慮及び中国との経済貿易発展による経済的困窮の解決、西側中心外交の失敗といった様々な諸要因により、ロシアが中国との関係を発展させるための手口を探し始めた」ことを指摘する(73頁)。
ここで議論されるべき点は中露関係の時期区分であろう。中国の研究者たちは「共通の見解」として、1)善隣友好期(1991年-94年9月)、2)「建設的パートナーシップ」(1994年9月-96年4月)、3)「戦略的パートナーシップ」(1996年4月以降)の三区分を採用しているが、「建設的パートナーシップ」と「戦略的パートナーシップ」の相違については共通了解がない
(3)
。著者は本書でより踏み込んだ独自の解釈を展開している。すなわち、「建設的パートナーシップ」から「戦略的パートナーシップ」への展開は中露関係がより高い段階へと発展したことを意味する。「建設的パートナーシップ」と「戦略的パートナーシップ」の相違点は、「第一に、戦略的パートナーシップはより高いレベルの関係である。……第二に、『建設的パートナーシップ』が両国の平等な相互利益を求め、互恵を関係発展の基礎とするのに対して、『戦略的パートナーシップ』はほとんどの場合、長期的な戦略上の利益を両国の関係を処理する際の基礎にしている。第三に、『戦略的パートナーシップ』は両国に共通する利益が犯された場合、両国の戦略目標の実現を目指して、損害を与えた第三国及び国家集団に対抗する可能性を排除しない。だが、『建設的パートナーシップ』は特定の第三者に向けられたものではない」(98頁)。
この最後の論点は注目に値する。1999年6月2日、中国中央電子台(テレビ局)は、NATOによるユーゴ空爆の最中、訪中したイワノフ外相と唐家 外相の会談を異例の長さにわたって報道した。その共同宣言は表面上、中露は「第三国」に向けて政治・軍事的提携をとるものではないとうたっていたが、日米安保とNATOに対抗する強いメッセージが込められていた(4)。「戦略的パートナーシップ」なるコンセプトが外に向けて発信される場合、それは固有に定義されたものではなく、国際情勢の推移に応じる変数として了解されるべきであろう。
外相の会談を異例の長さにわたって報道した。その共同宣言は表面上、中露は「第三国」に向けて政治・軍事的提携をとるものではないとうたっていたが、日米安保とNATOに対抗する強いメッセージが込められていた(4)。「戦略的パートナーシップ」なるコンセプトが外に向けて発信される場合、それは固有に定義されたものではなく、国際情勢の推移に応じる変数として了解されるべきであろう。
さて国際関係の次元では変数であったとしても、中露二国間の関係においての「パートナーシップ」はどの程度まで内実を伴っているのか。中国の研究者の多くがそうであるように、著者もここで経済貿易関係への分析へと向かう。著者は、中露の政治関係が進展しているのと対照的に、その経済貿易関係は1990年代初頭の不正常な国境貿易の増加を除けば、長期にわたって低迷した状態だと率直にみとめる。中国とロシアはともに貿易および科学技術協力を発展させたいとの希望を共有している。それは、双方の経済が相互補完的な特質があるだけでなく、中露両国がいずれも国境沿いの貧困地域を発展させたいという切迫した課題に直面しているからである。経済貿易関係の発展は双方の政治的関係に確固たる物質的な基礎を与えることになろう。
だが政治家たちの願いもむなしく、両国の実業家たちは西側との付きあいに熱中している。ロシアの低迷し、かつ予測可能性を欠いた経済、古い産業技術、さらに不安定な金融情勢などへの対処は、市場経済に対する備えが未熟な中国企業にとって容易ではない。さらに中国の国有企業改革は、政府による行政指導に基づいた売買の減少をもたらし、大部分が政府購入によってまかなわれている中露貿易に打撃を与えている。唯一の例外はロシアからの武器の輸入であり(165頁)、軍事技術交流と軍事協力は中露関係において相当な比重を占めている。著者は、第四章でそれをハイレベルな軍指導者の相互訪問、軍事専門家と各機関の交流、軍事力の相互削減及び軍事領域での信頼醸成措置の強化などに類別している
(5)
。
ところで中露間の経済貿易の発展にマイナスの影響をもたらしている非経済的な原因を、著者は次のように整理している。それは、第一に1991年の中露国境画定協定に対してロシア極東の政府担当者及び住民が繰り返す非友好的な言動、第二に極東への中国人移民に対するロシア人の警戒、第三に19世紀の植民地主義の時代や中国革命の際にロシアが中国に対して頻繁に行った様々な干渉である(116-118頁)。
国境画定が終了し、未来志向の中露関係が語られる現在、中露間の(とくに国境地域の)経済貿易の発展を阻害する要因は主に第二のものといえよう。中露国境開発の計画の多くが遅々として進まないが、これは中国人の進出に対するロシアの根深い警戒心がその理由である。この点は中露相互の民間レベルでの信頼醸成がすすまない限り、容易には解消されないだろう。著者は中露間の文化交流と科学・教育協力なども第四章で簡単に紹介しているが、西側との同種の交流と異なり、中露間のそれは実際的な交流よりも「相互の理解を高め、交流を続けている」ことへのシンボル的な意味が強い。交流がいまだシンボルとして要求されているところに中露関係の現状が象徴されているのかもしれない。
本書を構成するもっとも重要な特徴の一つは中露国境交渉に多くの頁を割いている点にある。これは国境問題が中国にとって緊要な問題であったことを意味するだけでなく、この問題が首尾よく解決されることへの確信と、それを広く一般に知らしめたいという意図を本書の叙述から感じることができる。ロシア政府が極東の地方行政府の反発にもかかわらず、国境交渉を誠実にすすめてきた事実を中国は重視する。本書が刊行された翌1997年の11月、紆余曲折を経ながらも図們江近辺から中蒙露三国国境へ向かう約4200キロの中露東部国境は、91年の「中露東部国境協定」が対象外とした三つの島を除いて画定終了が宣言されたのは記憶に新しいが(6)、中国と中央アジア諸国の国境画定においてロシアが後見役を果たしたとの、本書の指摘も大変興味深い。「もともとカザフスタン、クルグズスタン、タジキスタンは中国との間に国境問題が存在することを認めず、中国と国境画定交渉を行うことを拒否していた。中国は旧ソ連との間で行われてきた国境交渉の継続のために、ロシアに調停を求めた。その結果、中央アジア三国はロシアとともに四カ国での組織を構成して中国と国境交渉を行うというミンスクでの協議に調印した」(180頁)。この意味で中国とロシアの「パートナーシップ」は、二カ国間のみならず中央アジアという文脈においても検討する必要がある。この点には次節で立ち戻ろう。
さて中露関係の初期の展開において、中国に警戒感をもたせた争点として台湾問題があった。実はロシアと台湾の関係構築はソ連のペレストロイカ時代に端を発している。ソ連崩壊後、「ロシアは政治的には多元化、経済的には私有化の国家へと変わった。台湾当局はロシアの激変をいままでにないチャンスだと思い、積極的かつ主体的な姿勢で対ロシア外交活動を開始した。ロシア側も経済状況がより悪化し、この困窮を乗り越える道筋として台湾当局のアピールに熱烈に反応し、ロシアと台湾の関係は急速に改善された。中国政府が厳しい抗議を行ってはじめて、ロシアの最高指導部が干渉を行いこの動きをかろうじて止めた」(187頁)。
筆者は中露関係における台湾問題に関して最後に独自の節をもうけてこう論じている。後述するように、公の場において論じること自体がいまだに忌避される傾向のある台湾問題を積極的にとりあげた本書の意義は少なくないが、中露関係においては台湾以上に重要な存在であるモンゴルの問題について何ら言及されていないのは残念である。
本書を読み進めるにつれ、肝心な論点で読者は隔靴掻痒の思いを免れ得ないものの、本書が提示する中露「パートナーシップ」の実像は「政治的発展と経済的停滞」という私たちの現状理解とほぼ共通のものであり、かかる率直な反省にたち本書が中露関係に提示する個々の論点は興味深く、その全体像は客観的かつ説得的である。読者は筆者が踏み込めなかった論点を本書に対する批判の対象とするのではなく、その論点が欠如している意味をあわせて分析することで、中露の「パートナーシップ」が内外に抱える様々な難しさを読みとるべきであろう。
2. 「善隣友好」と「地域大国」のジレンマ
− 広程『中国と中央アジア新国家の関係』
広程『中国と中央アジア新国家の関係』
ところで「改革・開放」以後、国内の経済発展のため安定した国際環境を確立することは中国にとって基本的な対外戦略となったが、それは以下のような要因に後押しされたものである。1)資金・技術・先進経営のノウハウへの切迫した要求と国際社会に承認されたいとの希望、2)国内の経済発展における地域間不均等の是正と中西部及び国境地域を発展させる目論見、3)平穏とはいえない少数民族への注意及びポスト冷戦下のナショナリズムと宗教復興に対する警戒、4)外交における伝統的な力のバランスへの配慮、5)周辺国が中国の将来を懸念し、対抗措置を取ることによって中国の国内発展が阻害されることへの不安。これらの要因によって中国は周辺諸国と友好往来を強め、「善隣的な対外政策」をとるに至った。
だが「善隣友好」を目指す中国は、それと対立しかねない外交上の指向を内部に抱えている。それは第一に、「大国」たる夢をかなわぬものとした近代以降の屈辱的な歴史に対する忸怩たる思いと、現代の国際政治に伴う様々な不平等と欧米列強によるパワーゲームとに対抗する民族復興への猛烈な悲願であり、第二に周辺諸国で少数民族の分離・独立傾向が相次ぐなか、自国内の民族・宗教運動に拍車がかかることへの懸念である。要するに、「地域大国」への指向から中国外交はいまだ自由ではない。
「大国」と「経済発展」への模索は、確かに一つのメダルにおける表裏の関係とみなしうる。国家の統一及び安定は膨大な人口を持つ中国の生存と発展の必要な条件であり、少なくとも予見しうる将来において、アジア太平洋地域で相当の影響力を持つ大国になろうとしながらも、周辺諸国に警戒心を持たせないよう配慮する中国の外交戦略は理にかなったものといえる。とはいえ、「善隣友好」と「地域大国」という外交の二つの達成目標が両立しうる保障は必ずしもない。もし周辺諸国が「大国化」する中国を警戒し軍事力強化策を取れば、これはアジア太平洋地域の安定及び発展に損失を与えるだけでなく、中国に対してもさらなる軍事増強を強い国内の経済発展を阻害するだけでなく、「善隣友好」外交によって国境地域を発展させようという目論見も難しくなるからである。
中国の「地域大国」と「善隣友好」という二つの外交目標の舵取りを見極めるという観点からみて、ソ連崩壊により突如として登場した中央アジア隣国への外交ほど格好の素材となる対象はなかろう。この意味でポスト冷戦期の中国と中央アジア五カ国の関係を分析し、その一般性と特殊性、中国との関係史及び現在の関係、5カ国の対外政策の動向、目指す利益、横たわる困難などを論述した広程『中国と中央アジア新国家の関係』は、注目に値する著作である。東欧中亜研究所の先達は本書への書評をこう始めている。「中国と新たに独立した中央アジア諸国との関係の現状を客観的に論じて、中央アジア各国に対する中国の政策を正しく説明し、その政策形成について世間に知らせるのは我々の任務
である」
(7)
。本書は中国と中央アジア諸国関係についての一種の白書と位置づけられよう。
本書は八章から構成され、中央アジア各国の基本的な状況、中央アジア五ヵ国及び中国の外交戦略などが論じられているが、出版が1996年のため中央アジア諸国が独立して以来、90年代半ばまでしかカバーされていない。にもかかわらず、本書は中央アジア研究の第一人者によって書かれた、中国における数少ない中央アジア研究の先駆的業績である。冒頭で掲げた「善隣友好」と「地域大国」の二つの観点は本書においても通底している。
本書は第一に、中国内部の経済発展をどのように進めるかという視点から中国が中央アジア諸国との関係を展開する重要性を論じている。中央アジア諸国との国家間関係を積極的に発展させるのは、中国の「善隣友好」外交及び国内における経済発展の重点を中西部へ移す(「全方位開放」)という発展戦略に合致するばかりでなく、それは中国との関係を積極的に発展させたい中央アジア諸国の希望とも一致する。この中央アジア諸国との協力関係を全面的に強化し、中央アジア諸国をアジア太平洋経済協力のプロセスへと導き、促進させることは中央アジアの安定と中国国境地域の安定にもプラスとなる。これは中国の国益のみならず、中央アジア諸国の国益にもみあったものといえる(4-5頁)。
宇山智彦による中央アジア側からみた次のような指摘との見方はあい通じている。「……ロシアが不安定な以上、ロシアとの関係をある程度維持しつつも他の国との関係を進展させることが、中央アジア諸国の経済安全保障にとって不可欠であることは、もはや明らかである。西側諸国との関係は既に目立つ形で進展しつつあるが、中国が今後もダイナミックな発展を続けるとすれば、カザフスタンやクルグズスタンが中国を自国の経済発展の牽引車にしようと考える可能性は否定できない。すでに、中国のほうがロシアよりも予測可能で秩序立っており、原料需要が高い巨大な市場であってカザフスタン経済と相補性がある、という声はカザフスタンでも出始めている」
(8)
。
本書は第二に中央アジアの戦略的な位置、中央アジアにおける中国の外交目標及び利害関係のある諸国の動向・中央アジア諸国の選択肢などを地政学の視角から分析している。これは「地域大国」への中国の指向と密接に関わった論点であろう。著者は中央アジアに利益を有する諸国の情勢や動きをおおまかに紹介した後、中央アジアにおける中国の戦略意図と中国と中央アジア諸国の利益の何が一致するのかについて論じている(83-94頁)。著者はいう。「中国は中央アジアで自分の価値観に見あった地域を領有するつもりはない。……中央アジアにおいて中国が追求しているものは中央アジアの安定と繁栄である。……中国は中央アジアの安定に脅威をもたらす勢力を抑制しうるあらゆる国際的な勢力と協力し、イスラム原理主義と汎トルコ主義の中央アジアへの浸透を防ぐ用意がある。我々の目的は中央アジアの安定と繁栄にある」(254頁)。中央アジア諸国の安定を維持することで中国とロシアの利益は一致している。中国は中央アジアでのロシアの「特殊なプレゼンス」を尊重しており、これが中央アジアの安定を守る上での重要な存在だと認めている。
これはまるで秋野豊を彷彿させる分析である。「中国は、ポスト共産主義の中央アジアで勃興しつつあるナショナリズムや、イスラム民族主義あるいは民主化の波が新彊ウイグル自治区にも波及し、チベットや内モンゴルの分離主義運動を刺激することを恐れたのである。そのため中国は、中央アジア諸国との直接的な関係を強化した。同時に中国は、CISの枠内における中央アジア諸国間の関係、とくに中央アジア諸国とロシアとの結びつきが継続されることを強く望んだ。この点で、少なくともソ連崩壊後の数年間は、中国にとって、チャンスを得ることよりも安定こそが明らかに重要であった」
(9)
。
本書の分析を通読することにより、読者は中央アジアにおける中国政府の目標、実際の活動などを説得的に理解することができる。本書は中国外交研究者にとっても中央アジア諸国研究者にとっても必読の文献であり、その分析は明らかに西側の研究者たちと共通の言語をもつ水準のものといえる。実際、著者は国際的なプロジェクトにもしばしば招請されており、著者の見解は中国語以外の文献で知ることもまた可能である
(10)
。
しかしながら、残念なことに叢書という刊行スタイルを意識してか、本書はややもすれば中国政府の実施する政策のあとづけに終始している傾向も強い。著者の力量からみれば、学術的観点においても、政府への政策提言という実践的観点においても、より踏み込んだ分析もなしえたはずだ。例えば、先の評者は本書の欠点として、中国と中央アジアの教育・文化交流および民間往来の分析とシルクロードを始めとするその歴史的経緯への目配りの欠如を指摘している
(11)
。
さらに前節でとりあげた『ソ連崩壊後の中露関係』と比較すれば、本書が(102頁で唐突に、中国が中央アジア諸国と関係を樹立したことで台湾の進出意図を阻んだという言及があるにもかかわらず)台湾問題については、ふみこんだ言及をしていない点に奇異な印象を感じよう。繰り返しになるが、台湾問題は微妙なテーマである。台湾を中国の「一地方」という枠組で地域協力の問題として論じたものでさえ、一般雑誌への掲載は容易ではない
(12)
。本書のケースでは、台湾問題が中央アジアとの国境地域で微妙な政治的ニュアンスをもたざるをえない民族運動と結びつけて論じられかねないのを忌避したのであろうか。それとも台湾問題は中国と中央アジアの関係を分析する際には検討に値しないテーマなのだろうか。著者に聞いてみたいところである。
前書『ソ連崩壊後の中露関係』では詳細に言及された国境問題についもまた本書ではあまり触れていない。たしかに中央アジア諸国との国境画定交渉はロシアのそれと比べれば、より複雑で微妙な問題である。旧ソ連時代の交渉で中露東部国境と中央アジア諸国の対中国国境はあきらかに一体の、領土交換の可能性も含めた取引対象であった。1991年の中露東部国境協定で対象外とされたハバロフスクに近いボリショイ・ウスリースキー島はロシアが実行支配し、棚上げされたことが知られているが、これはタジキスタンのゴルノ・バダフシャン東部2万平方キロを中国がソ連から受け取る見返りであったといわれる。91年のソ連崩壊のためこの約束が反古と化し、前書が指摘したように当初中央アジア諸国が対中国境画定に反発していたことを想起しよう。
それゆえ、ボリショイ・ウスリースキー島が中露交渉で事実上、棚上げされ、ロシアの管轄にとどまっている現在、中国がタジキスタンに対する領土交渉で安易な妥協を行わないことが予見される。内戦の傷跡深いタジキスタンと中国との国境画定交渉は現在、あまり進展がないと伝えられる
(13)
。もっとも、タジキスタンと中国の国境は山で覆われ、通関所もなく交流の乏しい両国関係の現状からみれば、国境画定を拙速にすすめる理由はない。
対照的に、タジキスタン以外の中央アジア隣国、カザフスタンおよびクルグズスタンとの国境画定交渉はドラスティックに進展した。カザフスタンは1994年に、91年「中露東部国境協定」に似た協定を締結し、残された係争地も98年までに解決され、中国側は完全なる国境画定が終了した最初の相手として、いまやカザフスタンを高く評価している(ロシアとは「三島問題」があるため、完全に終わったとはいえない)。またクルグズスタンとも96年に国境画定協定を結んでおり、残された係争地の帰属も99年8月、江沢民とアカエフの間で補充協定が結ばれ全て解決された(14)。タジキスタンとの交渉はいましばらく難航が予想されるが、中央アジア諸国全体との国境の状況が著しく改善したことに疑いはない。もはや公の場で論じるのに障害はなかろう。著者の手からなる国境交渉についての分析を大いに期待したい。
本書が刊行されて以来、中央アジアをとりまく国際情勢は急変しているが、著者は早い段階で新しい情勢の行く先を見切っていたようだ。本書は1992年5月、CIS第5回サミットにおいてロシア、カザフスタン、ウズベキスタン、タジキスタン、トルクメニスタン、アルメニアで調印された集団安全保障条約と、94年にカザフスタン、クルグズスタン、トルクメニスタンが参加したNATOの「平和のためのパートナーシップ」計画への中国の注意を呼びかけているが(219頁)、特に後者に関しては「これは中国と中央アジアの関係に影響を与えないが、長期的にはNATOの『平和のためのパートナーシップ』が中国に何らかの不利な影響をもたらすのではないか研究すべきである」と述べた(222頁)。
これは慧眼であった。近年、アメリカの中央アジアへのプレゼンスに対する中国の警戒は強まっている。確かにイスラム原理主義を防ぐ点において中国とアメリカは共通目標をもつが(102頁)、アメリカの「汎トルコ主義」への支持と中国のそれへの警戒は米中両国間で先鋭な争点となっている。中国の眼からみると、トルコと協調しつつ中央アジアに進出するアメリカの行動は、ウイグルの「分離主義」への動きと重なってみえるからである。ユーゴ空爆以後、アメリカを始めとするNATOは「民族自決」を支持し、「主権より人権のほうが優先すべき」という主張を強めている。中国はコソヴォの事例が国内の「分離主義者」を刺激し、西側諸国の中国への「介入」を誘発することを警戒している。従って、チェチェンのように中国と同じ「民族問題」を持つロシアこそ、中央アジアにおいて中国が協力すべき相手となるのは明らかとなろう。中央アジアとの国境にウイグルなどの「民族問題」をかかえる中国は、NATO及びアメリカに対する警戒を強めつつある昨今、よりロシアとの「戦略的パートナーシップ」の強化に向かわざるをえない。中央アジアをめぐる国際情勢は、中露「戦略的パートナーシップ」の行方を大きく左右していくであろう。
他方でロシアの中央アジアに対する影響力にかげりが見え始める今、中国は中央アジア諸国への独自の関心も強めつつあるようだ。1999年には中央アジアに関する著作が三冊ほぼ同時に刊行された
(15)
。確かに著者が本書で述べているように「中央アジアは中国にとって第一の外交対象地域ではなく」(96頁)、基本的にこの傾向は今も変わってはない。彼らは中央アジアにおける中国のプレゼンスが過大評価され、警戒されることをむしろ恐れている。とはいえ同時に、中央アジア諸国の多様化を彼らは十分に見切っている。中立でわが道をいくトルクメニスタン、ロシアとの関係を重視するカザフスタン、クルグズスタン、タジキスタン、ロシア離れを強めるウズベキスタン。中国はこの地域でどのような「善隣友好」と「地域大国」の政策をとるのか思案している。そのなかで特筆すべきは、近年の中国にとってのウズベキスタンに対する関心の増加である。広程によれば、中国の対中央アジア政策は地政学的にも歴史的にも、また両国にまたがるウイグル人の存在から民族政策の観点からもカザフスタンを最重視してきたこれまでの政策から、ウズベキスタンをこれに劣らぬ重要国とみなし、カザフスタンとウズベキスタンの両方とバランスをとりながら、関係を発展させる政策へと変わったという
(16)
。ロシアの中央アジアでの「特殊なプレゼンス」を前提としたうえで、中国が今後どのような外交を仕掛けていくのか、目が離せない。
おわりに−「ポスト文革」世代の台頭
本稿で紹介した二冊は様々な制約を課せられながらも、中国の「学界」の現在において最良の分析水準を示したものである点、疑いはない。そして中国でこのような著作が相次いで公刊されたこともまた画期的といえる。このような傾向が今後ますます強まっていくという確信を評者はもつ。
この二冊のみならず冒頭に紹介した叢書のシリーズは、他に『現実主義−西側の行動の源泉』、『1970年代以降の中英関係』、『中東問題研究』、『中米関係の争点を読む』、『中日関係三論』など注目すべき秀作を揃えているが、1950年代生まれの著者が主にその任を担っていることをすでに述べた。だがこれは先駆けに過ぎず、次の若い世代がすでに登場しつつある。この新たな世代は単に若いという点にのみ可能性を秘めているものではない。振り返れば、今の社会科学院の中堅を担っている40歳代後半から50歳代の世代は、研究者として不遇であった。そのほとんどは研究者として修行すべき20代のもっとも重要な時期に下放され、研究活動に専念することができなかった。率直にいって、文化大革命が中国の研究水準の停滞にもたらしたツケは少なくない。しかし、50年代後半から60年代に生まれた文化大革命を知らない世代が一気に台頭してきた。
中国における中央アジア研究の第一人者となった広程は1961年生まれであるが、ソビエト政治史を一人で書き下ろした全5巻からなる大著(《 70年》,世界知識出版社,1998年)が江沢民の側近、汪道涵(海峡両岸関係協会会長)の眼にとまり、江沢民の激賞を受けたと伝えられる。
70年》,世界知識出版社,1998年)が江沢民の側近、汪道涵(海峡両岸関係協会会長)の眼にとまり、江沢民の激賞を受けたと伝えられる。 は昨年末から始まった社会科学院における一連の改革のさなか、一挙に東欧中亜研究所の教授・副所長へと昇任し、次の所長と嘱望されるが、これは決して例外ではない。57年生まれの対米専門家、王逸舟(世界経済国際政治研究所副所長)、62年生まれの対日専門家、
は昨年末から始まった社会科学院における一連の改革のさなか、一挙に東欧中亜研究所の教授・副所長へと昇任し、次の所長と嘱望されるが、これは決して例外ではない。57年生まれの対米専門家、王逸舟(世界経済国際政治研究所副所長)、62年生まれの対日専門家、 志剛(黒龍江省社会科学院日本研究センター)などリベラルで優秀な研究者たちが様々な領域で続々と表舞台に登場している。「学界」での重みの低下は否めないが、長年にわたる蓄積をほこる中国の旧ソ連研究は、その「改革・開放」が進むにつれ、私たちと共通の言語にたってその興味深い分析で刺激を与えてくれるであろう。
志剛(黒龍江省社会科学院日本研究センター)などリベラルで優秀な研究者たちが様々な領域で続々と表舞台に登場している。「学界」での重みの低下は否めないが、長年にわたる蓄積をほこる中国の旧ソ連研究は、その「改革・開放」が進むにつれ、私たちと共通の言語にたってその興味深い分析で刺激を与えてくれるであろう。
注釈