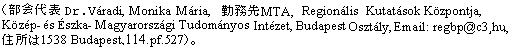ハンガリー社会学会の2000年全国大会が11月11-12日の2日にわたって同国南部のホードメゼーヴァーシャールヘイ市で開催された。筆者は最近の農村社会学の研究動向を知るため、この大会に出席した。
1970年代末に結成された同学会はこの10年で大きく発展し,会員数も現在では700名ほどに達している。ただし会員の中には学生や関連領域からの腰掛会員も多く、実際に社会学を大学や研究所で専攻している研究者は会員数の半分にも満たない。
ハンガリー社会学会は現在25の部会に分かれている。部会は会員の自発的発意により随時発足させることができ、大きく分けて三種類の部会がある。地域別部会,問題領域別部会、そして理論・方法論関連部会である。地方別部会には北東ハンガリー、北西ハンガリー、大平原地方、ペーチ地方があり、問題領域別部会には歴史、経済、軍事、スポーツ、フェミニズム、性問題、社会層、科学と工学、都市と住宅、青年、医療、環境と都市、教育、政治的態度、文化教養芸術、宗教、社会動態、農村がある。また理論方法論関連部会には社会学教育、理論と理論史、方法論がある。下線を施したのは今年の大会で分科会を組織した部会である。
今年の共通論題は「21世紀のリージョン化=ローカル化」だった。全体の議論を聞いてまず気づいたのは、リージョン(ハンガリー語ではレーギオーr馮i?jという言葉をEUリージョンに対応する地域単位として理解することが一般化しつつあるということである。現在ハンガリーにはブダペスト首都圏を入れて8つのレーギオーが設定されている。当初EUリージョンは「大きなレーギオー」というハンガリー語に置き換えられていたが、最近ではレーギオーがそのままEUリージョンの意味で通用し、公式的にもこちらがもちいられているのである。ただしポーランドなどとは異なり、ハンガリーのレーギオーには自治体としての機能はなく、地方振興予算の受け皿として上から政策的に設定された単位である。従って社会学者の間ではいまだレーギオーを分析の地域的枠組みとして受け入れることには抵抗が強いのであるが、かといってまったく無視するわけにはいかなくなっているのが現状である。
筆者は今回の全国大会では、個人的な関心から、またこの大会の直前にチェコでおこなわれた農業問題国際ワークショップ(本誌の別記事を参照)からの続きという意味でも農村問題に焦点を合わせていたため、もっぱら農村社会学分科会に参加した。もっとも社会学教育や政治的態度の分科会にも顔を出したかったのであるが、すべての分科会が大会2日目の同じ時間帯で同時進行するため、いくつかの分科会をかけもつことはできなかった。そもそも事前に報告要旨が配布されることもなく、さらに分科会の運営がすべて部会に任されていることもあり、他の部会には顔を出しにくい雰囲気があった。もっとも懇親会での出席者の様子などを見ていると、部会内での結束度が高く、分科会もワークショップ的性格が強い。従って日本で考える学会の年次大会とは様子が異なっている。実際にも報告ごとに出席者が分科会の間を動くというのは最小限だった。
農村社会学の分科会は今回の大会の中で最も報告数が多い分科会の一つであり、全部で10本にも上った。これを一日で済ますわけであるから、当然のことながら一報告あたりの時間は議論を含めて30-40分しかなかった。報告論題を並べると、「ハンガリーにおけるEUの地域振興助成金(SAPARD)」、「西と東:多様化する地方」、「ヨーロッパにおける新しい地方概念」、「1990年代における家族農場の労働と経営」、「サボルチ県におけるロマ調査結果」、「地方振興における自治体首長の役割」、「農村観光と地域伝統の再生」、「労使関係から見た農村立地製造業の類型化」、「南部平原地方における地方自治体と市民団体の組織運営」、「1990年代における大平原地方の散居農家調査」、以上である。昼食以外は休憩もなく、7時間あまりの過密スケジュールをこなさなければならなかったが、どの報告も筆者の関心を引くものばかりであり、あっという間に終わったというのが実感だった。
農村社会学部会で中心的存在であるI.コヴァーチ(科学アカデミー政治学研究所)の話では、1990年代前半に最も大きな関心を集めたのは体制転換に伴う農業の再編だったが、ここ数年は地方振興が中心的な研究論題になっているとのことである。彼自身も「新しい農村」という言葉を用いて、農村振興という問題に取り組んでいる。コヴァーチ氏はハンガリーの農村社会学者としては数少ない国際派であり、今回の報告(「ヨーロッパにおける新しい地方概念」)でも、「緑の輪Green Ring」のもとで西欧、東欧を超えた農村研究を呼びかける西欧の研究動向を紹介した。氏が主張する「新しい農村」論も「緑の輪」の一環として考えられているようである。ただし、西欧での「緑の輪」論には文化論が入っていなかったので、ぜひともこれを分析対象として取り上げるよう、西欧の同僚を説得した、という点をコヴァーチ氏は報告で強調していた。コヴァーチ氏は文化を国民文化として考えているようなので、筆者が、国民文化論は必ずしも農村と結びつくとは限らないのではないか、と質問すると、コヴァーチ氏は、「ハンガリーの国民文化は強く農村と結びついているし、西欧でもスカンジナビアなどでは国民文化は農村文化と表裏である」との答えが返ってきた。これは現在の農村社会学者が基本的な価値観としては戦前における人民派(農村派)の延長線上にあることを物語っている。ただし今の農村社会学者は社会主義時代に陳腐化した人民派という用語を自らに冠することには強い抵抗を持っている。
この点に関連してもう一つ重要なことは、ハンガリーの農村社会学者の意見が、ハンガリーに「農民paraszt」はいなくなったという認識で一致していることである。これはいまから20年以上前に、現代ハンガリー農村社会学の草分けであるP.ユハースが「我々は農民なのか? 農民のままでいるのだろうか?」とう問いを発した時にまで遡る大問題であるが、この10年で若手の社会学者達はきっぱりと結論を言い切るようになっているのである。いつの時点で農民がハンガリーから消滅したのかでは議論が別れるが、いずれにせよ1990年代初めにおける集団農場の解体と再編が農民消滅への最終的契機であったと考えられている。筆者はこの間のハンガリー農村社会学における論争を文献的にきちんと跡付けていないので、具体的にどのような議論を経てこうした結論に達したのか、ここで詳らかにできないが、この共通認識は興味深いし、重要である。というのは、農民なき後の農村社会学はいったい何を研究対象とするのか、が問われることになるからである。筆者は率直にこの問いを分科会の席上で投げかけてみた。農村的伝統という答えもあったが、I.コヴァーチ氏は「新しい田園」という答えを示した。この「田園」はハンガリー語のヴィデークvid駝の訳語である。ヴィデークは地方という意味でよく用いられるが、そこには田舎という意味も込められているので、農村社会学者達の意図を汲めば、田園という訳語が原語のニュアンスに最も近い。「では田園の内実は何か」と、筆者がさらに質問すると、コヴァーチ氏は一呼吸おいてから、「西欧と繋がる緑の輪としての田園的地方である」と答えた。この答えは緑の輪を文化論として論ずるべきだと主張するコヴァーチ氏としては苦しいものである。農村社会研究を環境や自然保護の視点からだけでなく、文化研究としてもおこなうのであれば、どうしても文化の担い手である人が登場しなければならない。農民がいないと宣言してしまったハンガリー農村社会学会が農民抜きの農村文化論をどう築くのか、農村社会学の存在理由をかけた大問題である。
先に、最近のハンガリーにおける農村社会学研究は地方振興が主たるテーマであると書いた。実は地方振興をテーマとした研究は、EUの地方振興補助金絡みで調査需要が多いのである。いま、ハンガリーの農村社会学者はそうした地方振興が実際には農村のアスファルト化以外の何ものももたらさないことに気付き始めながら、換骨奪胎的に転用されるとわかっている地方振興プログラムの作成に手を貸しているのである。今回の分科会参加者の一人は、これを「農村社会学者の自己矛盾と無力感」と表現していた。EUの地域振興助成は意図的に東欧農業の解体を狙ったものだという、極めて穿った見方を述べた者もいる。社会学者は時代情況を先取りして問題を提起する、という一般命題が正しいとすれば、ハンガリー農村の将来は真っ暗と言わざるをえない。
さて社会学会全体に話を戻すと、3年前から開催地を地方に移す試みを始めたそうで、学会事務局はその分だけ苦労が増えたが、地域の特色を盛り込んだ大会運営ができるため、面白くなったという声がある。と同時に、参加者が大幅に減少しているという問題点も指摘されている。確かに今のハンガリーで研究者が時間と旅費を使って学会だけのために地方に行くのは,容易なことでない。今回の大会参加者の多くは開催都市にある学生寮に泊まり、分科会会場もこの学生寮の勉強室が当てられた。大会2日目の昼食は前日夜の懇親会料理の残りという、見事な節約ぶりだった。もっとも当の懇親会では肉料理主体のたっぷりとした献立が用意され、さすがは食べ道楽を自認するハンガリー人だけのことはあった。
ところで筆者にとって開催都市のホードメゼーヴァーシャールヘイへは10年ぶりの再訪であり、なつかしい記憶が蘇った。その一方で新たな発見もあった。というのは、市の好意で共通論題の会場に市庁舎の大会議場(ここで市議会が開催される)が使えることになり、100年以上前に建てられた由緒ある会議場に足を踏み入れることができたのである。発見というのはこの会議場そのものではなく、会議場に飾られていた等身大をはるかに越える肖像画の顔ぶれである。まずはハプスブルク皇帝フランツ・ヨーゼフと皇后エリーザベトである。二人の肖像画は少なくとも社会主義時代から一貫して掲げられていたとのことである。市会議員は背後から皇帝と皇后に見おろされて議事を進行する配置になっている。そして議場側面の壁ではハンガリー史に名を残した三人の著明な政治家、ラーコーツィー二世、デアークそしてアンドラーシが議場を見守っている。筆者は、実をいうと,この地域の歴史的な経緯から判断して、ホードメゼーヴァーシャールヘイ市を含むハンガリー平原南部地方は革新的,かつ共和主義的だと思い込んでいたのである。しかしこの議事場の肖像画を前にして、はたと考え込んでしまった。
大会終了後、ブダペストに戻って、旧友のGy.ケヴェール氏(ブダペスト大学社会経済史学科教授)を尋ねて「ホ市の議事堂に誰の肖像画が飾ってあったか、当ててみよ」と意地の悪い質問をしたところ、彼も共和派政治家の名前をまず挙げた。正解を告げると、それは彼にとっても意外だったようだ。ハンガリー史を志すどなたか!この難問に取り組んでみませんか。
ともあれ、あれこれと収穫の多い学会参加ではあった。もっとも筆者は今年の分科会の席であれこれコメントをつけたので、成り行き上、ハンガリー社会学会の会員、および来年度の大会報告というおまけまでついてしまった。読者諸氏の中でハンガリー社会学会と接触をもちたい方、報告したい方は、筆者まで御連絡ください。農村社会学部会へは直接問い合わせることも可能です